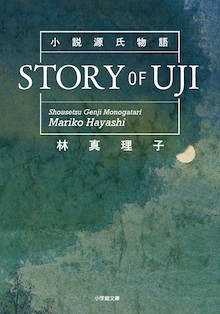お知らせ
2019.4.14
マンガで読む。巨匠で読む。日本古典文学
この記事は掲載から10か月が経過しています。記事中の発売日、イベント日程等には十分ご注意ください。
日本古典文学の名作をベテラン漫画家が原典に沿ってビジュアル化!
混迷の時代に、千年の時を生き抜いた日本の古典が、より親しみやすい形で甦る!
各ベテラン漫画家ならではの漫画化で、古典作品の魅力が倍増!
読み応えと格調のある内容で、大人の古典鑑賞、入門に最適です!
世界の神話・伝承に造詣の深い里中満智子が描く「物語としての古事記」
イザナキとイザナミ、アマテラス、スサノヲ、オオクニヌシ、ヤマトタケル・・・・・・
日本誕生ロマン『古事記』を、世界の神話・伝承を描いてきた里中満智子が、女性ならではの視点で描写。
‹‹現代では「古事記」を「こじき」と読むのが一般的ですが、本書では「やまとことば」の「ふることふみ」と読んでいただきたいと思いました。日本には民族の言語として「やまとことば」がありました。漢字の輸入により「やまとことば」に漢字の音をあてる「あて字表記」も使われましたし「音よみ」も使われるようになりました。しかし・・・・・・古代より伝えられた「神話」は「やまとことば」で語られたはずです。
古事記に登場する固有名詞がみな「やまとことば」で読まれるのにタイトルだけが外来語発音というのはどうにも納得がいかなかった・・・・・・からです。
江戸時代の学者 本居宣長は35年の月日をかけて「古事記」の注釈書である「古事記伝」全44巻をまとめました。本居宣長は「ふることふみのつたえ」と発音していたといわれています。
古事記に描かれている事柄や人物などについては古来よりさまざまな解釈がなされています。「これは事実ではない」「この人物は実在しない」など色々な見方や考え方があります。また数多くの解釈、解説書もあります。
私は、今回この作品を描くにあたって「物語としての古事記」のつもりで描きました。
ですから「学問としての解釈」と必ずしも一致していない部分があることをご理解ください。
これをきっかけに「古事記」そのもの、また「解釈」に興味をもってくださる読者がふえることを願っています。››(著者「本文」より)
この巻では、「天の岩屋戸」「八俣大蛇」「大穴牟遅」「根之堅州国」「大国主神」「国譲り」「天孫降臨」「木花之佐久夜毘売」「山幸彦と海幸彦」「豊玉毘売」「神武東征」「天皇誕生」「欠史八代」などを収録。
巻末寄稿は竹田恒泰さん。

著/里中満智子
【著者プロフィール】
里中満智子(さとなか・まちこ)
1948年1月大阪生まれ。1964年、高校在学時に「ピアの肖像」で第1回講談社新人漫画賞受賞、デビュー。
2006年に全作品及び文化活動に対し、日本漫画家協会賞文部科学大臣賞受賞。2010年文化庁長官表彰受賞。
代表作に「あした輝く」「アリエスの乙女たち」「海のオーロラ」「あすなろ坂」「狩人の星座」「天上の虹」「マンガ ギリシア神話」「マンガ 旧約聖書」など多数。
日本漫画家協会常務理事/マンガジャパン代表/大阪芸術大学キャラクター造形学科教授など。
花村えい子の繊細華麗な筆致で日本女流文学の最高傑作が蘇る!
桐壺帝の第二皇子として出生し、才能・容姿ともにめぐまれながらも臣籍降下して源姓となった光源氏が、平安王朝を舞台に数多の恋愛遍歴を繰り広げる『源氏物語』。
この波乱の宮廷ドラマが、多くの文芸・ミステリーを原作とする作品を手がけているベテラン漫画家・花村えい子の手により、いきいきと甦ります。
解説は代々木ゼミナール講師・望月光さんです。
‹‹紫式部が『源氏物語』を書いた平安時代中期、ヨーロッパはまだ、一部の歴史家に「暗黒時代(ダークエイジ)」と呼ばれるような時代でした。文章だって幼稚なものしか書けなかった。そんな時代に、日本人の女性がこれだけ完成度の高い長編物語を書いたということは、日本人が誇りにしていいことだと思うんです。日本にもし『源氏物語』という作品がなかったら、私たち日本人は、ルーブル美術館に行って、とても胸を張って歩けなかったかもしれない。
事実、1999年に、イギリスのオックスフォードやケンブリッジの歴史学者が「この千年間で偉大な業績を残した歴史上の30人」というのを選んだときに、日本人ではただひとり紫式部が選ばれました。
世界の30人ですよ!
『源氏物語』は日本文学の最高傑作というより、世界規模の文化遺産なんですね。
<中略>
みなさんも花村先生のマンガで『源氏物語』を楽しまれたあとは、ぜひ原文に挑戦してみてください。
今すぐでなくてもかまいません。
年配の方は今すぐでも差支えありませんが、若い方たちは、お年を召してからの方がいいと思います。
『源氏物語』は大人のための世間話ですから。››(望月光氏「作品解説」より)
上巻では「桐壺」「帚木」「空蝉」「夕顔」「若紫」「末摘花」「紅葉賀」「花宴」「葵」「賢木」「花散里」「須磨 其の一」を収録。
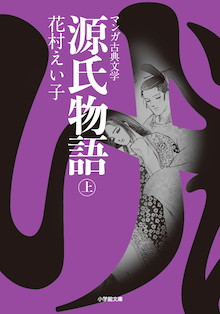
著/花村えい子
【著者プロフィール】
花村えい子(はなむら・えいこ)
埼玉県川越市出身。女子美術大学絵画科中退。1959年貸本漫画「別冊・虹」掲載の「紫の妖精」でデビュー。
以降「なかよし」「少女フレンド」「マーガレット」「少女コミック」他各誌で少女漫画のパイオニアとして活躍。その後、「女性セブン」をはじめとする女性誌に活躍の場を広げ、文芸・ミステリーを原作とする作品等を発表し続けている。
代表作に「霧のなかの少女」「花影の女」「落窪物語」等。
1989年第18回日本漫画家協会賞優秀賞、1997年第1回メディア芸術祭マンガ部門大賞受賞。
フランス国立美術協会(ソシエテ・ナショナル・デ・ボザール)正会員、日本漫画家協会理事。
水木しげるが『方丈記』の世界を無常の歌人・鴨長明の生涯を交えながら活写!
日本三随筆のひとつ『方丈記』の作者であり、平家興亡・源平争乱の平安時代末期に多くの厄災を体験した無常の歌人・鴨長明。
水木しげるが、長明の生涯を交えながら、中世の天変地異ドキュメント『方丈記』を完全にコミック化しました!
‹‹『方丈記』は〝無常〟すなわち、あきらめの心情に最初から貫かれている。水木サン(著者)は若い頃、出征する前に『方丈記』を読んで、大いに共感を覚えた。死に行く者はあきらめの境地にならなければならなかったのだ。しかし今の時代、すべてを容認してあきらめずに困難に立ち向かう姿勢こそが、大事なのかもしれない。
その頃(『方丈記』執筆前後)の長明は、『無名抄』や『発心集』を記している。『無名抄』を読むと、ある種の郷愁のようなものが感じられるね。また、『発心集』の仏教説話なんかは、長明の感じる〝無常〟の心が反映されているのだろう。
長明が死んだのは建保四年(1216)閏6月10日という。享年62歳であった。
世を恨んで出家した長明の心には、都を捨てたといいつつも、都の生活を惜しんでやまない気持ちがあったと思う。最後は方丈の庵で、人知れずひっそりと死んでいったのだろうな。
長明の〝無常感〟は、若い頃の災害、挫折の経験が大きかったのだろう。21世紀の現在でも、大いなる災害などの問題を抱えている・・・。この閉塞感は『方丈記』で語られる〝無常〟と無縁ではないだろう。››(著者「本文」より)
仏教的無常観を主題に、作者の体験した都の生活の危うさ・はかなさを、大火・辻風・飢饉・疫病・地震・遷都等の実例によって描き、ついで移り住んだ日野山の方丈の庵の静寂な生活を記した随筆。
巻末寄稿は荒俣宏さん。
作品解説は関口浩(駿台予備学校古文講師)さん。

著/水木しげる
【著者プロフィール】
水木しげる(みずき・しげる)
1922年生まれ。鳥取県境港市で育つ。本名、武良茂(むらしげる)。幼少時、近所に住む老婆「のんのんばあ」から不思議な話や妖怪の話を聞き、強い影響を受ける。太平洋戦争時、激戦地であるラバウル、ニューギニア戦線に従軍。爆撃を受け左腕を失う。復員後、魚屋、輪タクなどの職業を転々としたのち、神戸で紙芝居作家となる。その後単身上京し、貸本漫画を描き始める。
1957年「ロケットマン」でデビュー。1966年「テレビくん」で講談社児童漫画賞を受賞。1968年「ゲゲゲの鬼太郎」がアニメ化され、テレビ放映。1991年、紫綬褒章受章。2003年、旭日小綬章受章。2007年「のんのんばあとオレ」で仏アングレーム国際漫画祭最優秀作品賞受賞。2010年文化功労者に。2015年93歳で逝去。
代表作に「ゲゲゲの鬼太郎」「河童の三平」「悪魔くん」「日本妖怪大全」「水木しげるの遠野物語」など。
☆ 本シリーズの今後の発売予定です!
5月2日発売予定
・『古事記(中)』著/里中満智子
・『源氏物語(下)』著/花村えい子
6月6日発売予定
・『源氏物語(下)』著/花村えい子
・『伊勢物語』著/黒鉄ヒロシ
7月5日発売予定
・『竹取物語』著/池田理代子
・『徒然草』著/長谷川法世
★こちらもオススメ!
・現代語訳と原文で気軽によめる!『日本の古典をよむ[1] 古事記』
・里中満智子が描く壮大なエジプト叙事詩!『アトンの娘 [1]』
・花村えい子 伝説の少女漫画を単行本化!『完全復刻版 霧のなかの少女』
・この三角関係、人ごとじゃない。林真理子版「源氏物語」『小説源氏物語 STORY OF UJI』
・東西妖怪絵の集大成となる1冊!『水木しげる 世界の妖怪百物語』
関連リンク