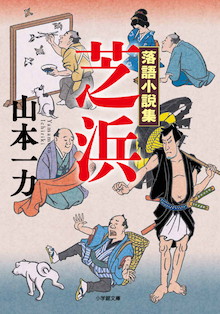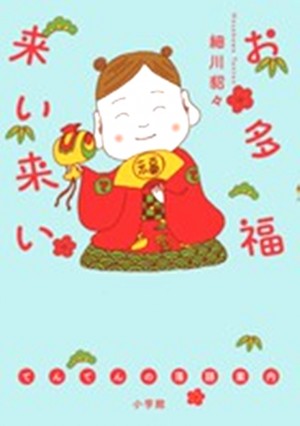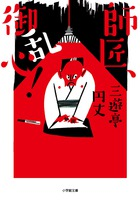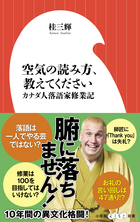お知らせ
2019.5.26
さだまさし氏絶賛!これぞ「上手いしゃべり」のお手本!『噺のまくら』
この記事は掲載から10か月が経過しています。記事中の発売日、イベント日程等には十分ご注意ください。
昭和の大名人が遺した噺のまえの「まくら」のみを選りすぐり65篇
六代目三遊亭圓生(さんゆうていえんしょう)は、落語の本題の前に喋る短い話「まくら」の名手としても知られていました。
数々の名高座から「まくら」65篇を選りすぐり!
圓生落語同様、笑いの中にも品格を感じさせる、粋な話芸の世界が存分に楽しめます。
本題の噺への導入になっているものもあれば、噺を理解するための解説や伏線の役割を果たすもの、オチまでついてそれだけで一つの作品になっているものも。
落語の舞台である江戸時代から、圓生が生きた明治、大正、昭和の時代までの文化、歴史、風俗、しきたりなどが、生き生きとした洒脱な江戸言葉で語られます。
下々の生活実情に興味を抱く無邪気なお偉方たちのあれこれ「大名の飯炊き」、昔の葬式の風習を笑いも含めて伝える「とむらいの作法」、チップによる遣手おばさんの対応差「吉原の祝儀」などなど。
「へぇ~」となったり、「クスッ」と笑えたり。
稀代の名手による、一冊丸々読む「まくら」。
面白くて、ためになる、しゃべりのヒントも満載!
圓生さんを知らない世代にもぜひ読んでいただきたい名書です。
さだまさしさんによる落語愛あふれる解説文も読みごたえたっぷり!
‹‹古典落語は話しながらたとえ内心「この噺(はなし)はつまらない」と思って居ても、当の演(や)り手への余程の評判や本人の自信でも無い限りその「筋」を変えたり「下げ」を変えたりすることは難しいようだ。
そこで演り手にとっては「まくら」が己を表現する手っ取り早い道具になる。
誰でも知っている噺ならばすぐに上手の誰かと比較されるけれども「まくら」は個人のものだからだ。
それで割合自由に出来る分、その人の思想や視点、考え方や価値観までが浮き彫りにされるからある意味では一番怖いものだろう。
つまりその人がどの程度の人物であるか「まくら」を聞けばおよその目途が立つ。
噺は上手(うま)いけれども「まくら」のつまらない人が居(お)り、「まくら」は面白いが噺が下手な人がある。
どちらも上手い人は少ないが三遊亭圓生はそのどちらも上手の中の上手だ。
最初に結論を言う。
本書に触れて誰もが思うことだろうが、三遊亭圓生の頭脳と知識こそが既に偉大なる「文化」そのものであり、その演目の多さ、多彩多様な上手さは、落語家の一人というだけではなく、『三遊亭圓生』という一個の「ジャンル」であったと思い知る。
こういう人をこそ『名人』と呼ぶべきであってまさに三遊亭圓生は『日下開山(ひのしたかいさん)』と称えられるべき巨人であったと思う。››(さだまさし著【解説】圓生の頭脳と知識こそが偉大なる「文化」)
著/三遊亭圓生
★こちらもオススメ!
・昭和の大名人が語る芸、寄席、粋な生き方。『浮世に言い忘れたこと』
・直木賞作家が「落語の人情世界」を小説化した小学館文庫『落語小説集 芝浜』が今、売れています!
・〝ネガティブ思考クイーン〟の漫画家・細川貂々さんが落語と出会って目からウロコ!『お多福来い来い てんてんの落語案内』
・「落語の笑いは世界共通、みんな同じところで笑ってくれる」『空気の読み方、教えてください カナダ人落語家修業記』
関連リンク