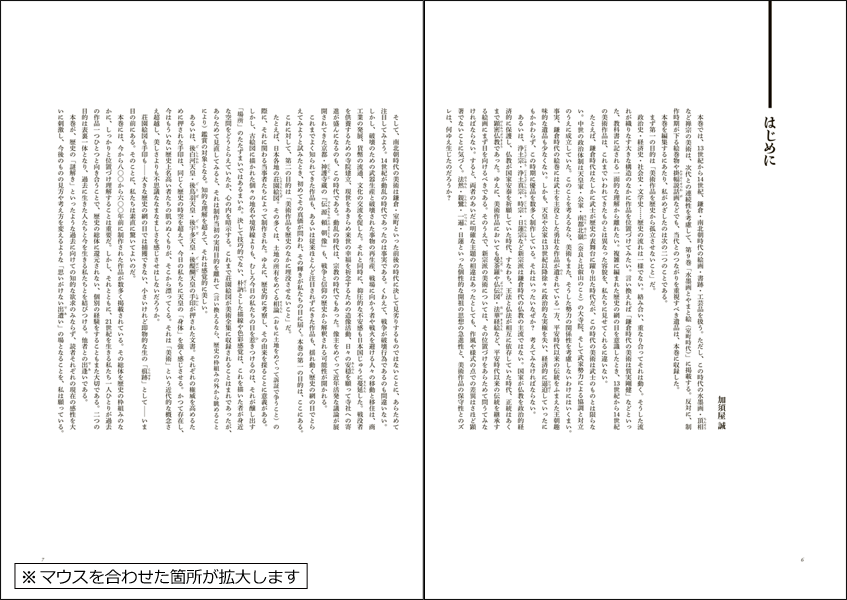日本の心が紡いできた比類なき「美」。「日本美術全集 全20巻」。今、日本に存在する「最高の美」のすべてがここに。
第16回配本 中世絵巻と肖像画(鎌倉・南北朝時代Ⅱ)
| 責任編集/ | 加須屋 誠(奈良女子大学教授) |
|---|---|
| 定価 | 本体15,000円+税 |
| ISBN | 9784096011089 |
| 判型・仕組 | B4判/304頁 カラー図版口絵144ページ・カラー図版両観音16ページ モノクロ解説ページ144ページ/上製・函入り/月報付き |
もくじ
- はじめに 加須屋 誠(奈良女子大学教授)
- 鎌倉・南北朝時代の絵画・書跡・工芸 加須屋 誠(奈良女子大学教授)
- 「まなざし」の歴史学──王法と仏法の歴史学 加須屋 誠(奈良女子大学教授)
- 鎌倉時代やまと絵の形成──尊智・円伊・高階隆兼 谷口耕生(奈良国立博物館)
- 「肖像画の時代」の肖像画 黒田 智(金沢大学教授)
- 鎌倉時代南都の舎利荘厳美術 内藤 栄(奈良国立博物館)
- コラム/中世書跡の和様と唐様 宮崎 肇(東京大学史料編纂所特任研究員)
- コラム/中世武士の装い──軍記物語にみる甲冑の威毛 宮崎隆旨(元奈良県立美術館館長)
概要
本全集20巻のうち、鎌倉時代の美術を中心に扱った巻は2巻あり、一冊はすでに刊行している第7巻『運慶・快慶と中世寺院』(鎌倉南北朝Ⅰ)です。47体の運慶仏を中心とした彫刻作品や寺社建築を中心に掲載した7巻に対して本巻は、絵巻物や肖像画、仏画などの絵画を中心に、書跡や甲冑・刀剣などの武具のほか、蒔絵手箱などの漆工作品に舎利容器などの仏教工芸を取り上げています。
武士の台頭とともに貴族の勢いが衰えたこの時代は、美のありようも大いに変化しました。現実の風景に宗教的な幻想を重ね合わせたかのような絵巻物が制作される一方、迫真の肖像画が描かれたのもこの時代です。本巻では、180点余のカラー図版と論考・コラムを通じて、鎌倉南北朝期の人々の美意識、人間観、世界観をあきらかにします。
注目点
この巻は、第一章「絵巻物」、第二章「掛幅説話画と古絵図」、第三章「人の姿かたち」、第四章「仏画と垂迹画」、第五章「書と工芸」という全5章の章立てとなっています。以下、章立てに添って、さらに細かい編者の意図を小見出し(「」が小見出し。本巻には未掲載)のもと、見どころの一部を紹介します。
第1章 絵巻物
平安時代にひとつの達成をみた絵巻物は、この時代、その精華を受け継ぎつつ多様なヴァリエーションをみせます。まず冒頭は「武士の世の到来」で、平治物語絵巻や巻の箱にも使用した後三年合戦絵巻などを掲載。さらに、様々な階層の出現を表現した《東北院職人歌合絵巻》なども紹介しています。次に「王朝文化を追慕する」という括りで、《玄奘三蔵絵》《春日権現験記絵巻》《紫式部日記絵巻》などが登場、天皇・貴族たちの、ありし日の華やかな暮らしを並べます。「世俗と交わる僧侶たち」では、《法然上人絵伝》《一遍聖絵》ほか7作品で、伝統的な古い仏教と、それに対抗する新しい仏教の諸相をみます。そして、この章の最後は、「縁起絵と経絵」で、《當麻曼荼羅縁起絵巻》《観音経絵巻》のほか、美術全集では紹介されることの少ない《北野天神縁起絵巻(弘安本)》などの作品を掲載しています。
第2章 掛幅説話画と古絵図
この章は、経論に基づく説話画を宗派的に分類して掲示する「教理を伝える」で、《釈迦誕生図》《十界図》のほか、13世紀を代表する絵画作品《六道絵》を部分拡大を効果的に用いて掲載。続く「歴史を創作する」「場所を記憶する」においては従来の美術全集では掲載されることが少ない《称名寺絵図》《祇園社絵図》などの古絵図が注目です。
第3章 人の姿かたち
巻のタイトルにもなっている肖像画。鎌倉時代は、肖像画の時代といっても言い過ぎではない時代です。平安時代までは、一部の高僧の肖像画が伝わっていますが、この時代には、僧侶に加えて、公家、武家の肖像画が数多く描かれました。「個性を写す」では、描かれた人物を「個人」として捉える思想と感性の萌芽を作品にみます。《鳥羽天皇像》《崇徳上皇像》《後白河法皇像》といった天皇像のなかでも特に注目なのは、対看写照(本人を目の前にして、その姿を写しとること)によると伝わる《後鳥羽天皇像》と、“異形の王権”南朝の《後醍醐天皇像》です。
そして像主をめぐって何かと話題の《伝源頼朝像》は、全図に加えて顔貌をクローズアップで掲載、像主特定論とは別に、この時代を代表する肖像画の白眉を眼前にします。そのほか、「連なる神・仏・人」「尊敬と追慕」では、最近修理が終わった《若狭国鎮守神人絵系図》や《明恵上人像(樹下坐禅像)》などを掲載しています。
第4章 仏画と垂迹画
この章は、《山越阿弥陀図》《仏眼仏母像》《十体阿弥陀像》など鎌倉時代を特徴づける完成度の高い仏画に加えて、いままであまり注目されなかった南都の仏画を紹介。さらに神が姿を変えてあらわされた様々な作品を「神仏の顕現」という括りで紹介する一方、宮曼荼羅など、聖なる場所を主題とした《春日宮曼荼羅図》《熊野宮曼荼羅図》などを掲載、特に《那智瀧図》は、単なる風景画ではなく宗教画であることがわかります。
第5章 書跡と工芸
絵画に残された痕跡は多くのことを伝えてくれます。ただ、この時代の気配がもっとも感じられるのは、もしかしたらこの章に掲載した書跡かもしれません。最初のページに掲載するのは、後白河天皇の手印が押された《文覚四十五箇条起請文》です。赤くくっきりと押された手印は実物大で掲載、その生々しい身体感が眼を惹きつけてやみません。続く、後鳥羽、後宇多、後醍醐天皇の手印が押された書跡も注目です。ほかにも、明恵、法然、親鸞、日蓮という歴史に名を残す高僧の直筆が個性あらわに眼に迫ります。
書跡の次は、武具を取り上げます。鎧、胴丸のほか、刀剣に箙(えびら)、弓など、ほとんどが実用というよりは神社などに奉納されたものですが、その造作の見事さに、あらためて武士の時代を意識することになるでしょう。最後に掲載するのは、平安時代よりも技巧的かつ理知的な表現が多くなった蒔絵工芸と、この時代に著しい発展を遂げた舎利容器などの仏教工芸です。いずれも伝統性と革新性の両面を有した作品といえるでしょう。
(編集担当・河内真人)
本巻で4巻目の美術全集を編集しましたが、各監修の先生に共通するのは、何よりも「目(眼)の力」です。私と比較するのもおこがましいのですが、同じ作品を見ていても、見ているもの、見ていることはまるで違う気がします。それはもちろん、学びに依るところもありますが、そうではないものを強く感じます。この「目(眼)の力」は、どう養われ、そしてどう使われているのでしょうか。本巻の監修者、加須屋誠先生に、その秘密? の一端をうかがいました。

加須屋誠先生、自宅書斎にて。
──なぜ美術史の研究を志したのでしょうか
子どもの頃、友達の少ない(ほとんどいない)子でした。特に嫌われていたわけではない(と思う、たぶん)のですが、目立たないというか、影が薄いというか。あなたの近くにも、そんな子はいませんでしたか? 覚えていないかもしれませんが、きっといたはずです。そして、そんな子は一体全体いつも一人でなにをしていたのだと思います? 教えてあげましょう、ただじっと見ていたのです。授業中に先生が黒板に書く文字のかたち、同級生たちの身振り、窓の外の空の色。ともかく、ただじっと見ている。すると、ぼおっとしていても、ときどき意識が覚醒する瞬間が訪れます。あの先生の字のハネは力強い(暴力的なほどに)、サッカー部のあいつが文芸部のあの子に話しかけると、彼女はいつも自分の髪を触る(恋愛感情の表れ?)、異常なほどに真っ赤な夕焼け(大地震の予兆か?)。
大仰な「芸術」とかお洒落な「アート」とか、そういったものに私は興味ありません。私が関心があるのは、ただ見ることだけです。それが理由で、私は大学で美術史を専攻しました。今は大学で美術史を教えています。相変わらず、影は薄いです。
──そのなかでも、今の専門を選んだきっかけを教えてください。
大学2年生のときに、大串純夫さんという戦前の研究者がお書きになった「来迎芸術論」という論文を読みました。それまで重々しくて動かないものと思っていた仏さまが、動いて見えるようになりました。歴史を探究することによって視覚が研ぎ澄まされる。知性と感性とが融合する学問のすごさを知りました。
大学院では、中野玄三先生の授業を聴講しました。先生からは、その後も長く(2014年にお亡くなりになる直前まで)、公私にわたり様々な教えを受けました。なかでも、目に見えているものの背後には、目には見えない世界があることをリアルに教わりました。20歳前後の多感な時期に戦争を体験された、先生の人生(人間性)と関わるような、抜き差しならないリアリティーです。
私の専門は仏教絵画史。特に来迎図・六道絵など、生死の問題と深く関わる、幻視性の高い絵画に惹かれます。

恩師の中野玄三先生と。
──わが生涯、感動! の5作品とその理由を教えていただけますか?
阿弥陀聖衆来迎図(高野山有志八幡講十八箇院)
来迎図は、人が死を迎えるときの苦痛を軽減し、死の恐怖を救済(極楽往生)の至福へと変換してくれる、見事なイメージ装置です。私の卒業論文のテーマでした(1984年)
子島曼荼羅(奈良・子島寺)
紺色の絹に金銀泥で尊像が描かれたマンダラは、宇宙の神秘を目の当たりに見せてくれるようです。私の修士論文のテーマでした(1987年)
二河白道図(京都・光明寺)
二河(火河と水河)の間にある白い道を渡ると極楽に行ける──象徴性の高い作品ですが、よく見ると、これが作られた当時(鎌倉時代)の現実の社会状況などを読み解くことができます。私の学会デビュー論文のテーマでした(1991年)
病草紙(京都国立博物館ほか)
「病気」という特異な主題の絵巻物ですが、「古代の終焉~中世の開幕」という歴史の転換期の価値観の揺らぎを的確に映し出しています。「他者」「まなざし」といった私の研究の核になる概念を使ってはじめて書いた論文のテーマです(2000年)
六道絵(滋賀・聖衆来迎寺)
仏教的な宇宙の構造(六道の具体的な様相)を全15幅にわけて緻密に描写した、日本の説話画の最大最高の傑作です。研究を志してから、それを一冊の本にまとめるまで20年の歳月がかかりました(1988~2007年)
振り返ってみると、その時その時、いつも一番好きな作品ばかりみつめてきました。
──研究に教育、その他様々な仕事でお忙しいと思います。普段の生活は、どのような感じでしょうか。
私の研究にはドラマチックな事件は一切なにも起きません。淡々としています。
毎朝4時に起き、6時まで机に向かいます。それから家族全員の朝食を用意(子どものお弁当を含む)。7時に奥さんと子どもを起こして、一緒にご飯を食べます。8時に家を出て大学に行く。大学では勉強しません(講義・会議・学生相談など、忙しくて不可能)。それらをうまくこなせれば、19時頃に帰宅。それから夕食。21時からは気が向けば史料を読むし、気が向かなければ小説を読んだり、ヴィデオを観たりします。23時前には就寝。
規則的にこうした生活が続けられれば、それはよろこびです。しかし、いろいろなことがあって、このペースを維持することがなかなか難しいのです。
私語りは苦手です(なにせ、影が薄いもので)。それよりも、第8巻「中世絵巻と肖像画」の話をいたしましょう。その方が、きっとずっとおもしろい。
──第8巻を通して、美術史とはなにか、美術史を学ぶことのよろこびなどを教えてください
第8巻では鎌倉~南北朝時代(13.14世紀)の絵画・書跡・工芸を扱います。しかし、この時代の美術は決してよく知られているわけではありません。
あなたは、小中学校あるいは高校の社会科(日本史)の授業で、中世の美術=「質実剛健」といったキャッチフレーズを教え込まれませんでしたか? なるほど、学校のテストはそれを暗記すればOKでした。けれども、実際の美術の歴史はそんなに単純ではありません。今に遺るひとつひとつの作品は、どれも、ひとりひとりの作家が丹精込めて、作り出したものです。そこに目を向けなければなりません。作品や作家の個性に注目することこそが、美術史の醍醐味です。
では、何百年も前の時代の作品や作家の個性を見極めるためには、どうすれば良いか。
そのためには、まず第一歩として、この時代を生きた人たちがどんな暮らしをして、いかなることを願い、なにを恐れたのか、具体的に知ることが大切です。美術は実生活から遊離したものではなく、社会の中で作られ、社会のために機能するものですから。
こうした過去の人たちの生活や心情は、知れば知るほど、それが私たち現代人と異なることに気がつきます。ところが、その一方で遠い昔の人が描いた絵画や愛用した工芸品を見ると、彼らと同じように私たちも、それを美しいと感じる。考えてみれば、とても不思議なことです。言うならば、時間と空間を越えて「他者」と通じ合うこと──彼らと対話する機会を、美術作品は与えてくれるのです。この時空を越える不思議に驚くことが、第二歩です。
そして三歩目は、「他者」との対話を通じて、ひるがえって「自己」とは何か? と自分に向かって問いかけることが大切です。私たち自身の生活や心情そして美意識は、一体なにに由来しているものなのかを考えること。もしかしたら、私たちの物の見方や常識なんて、薄っぺらで偏見に満ちた、歪んだものなのかもしれません。目の前にある古い美術作品を見ながら、反省します。喩えるならば、古い美術作品は、現在の自分自身を映し出す、鏡のようなものなのです。
ひとつひとつの作品をきちんと歴史に位置づけ理解すること、それはとりもなおさず、今を生きる私たちが自分自身の人生や心情を省みる機会となります。単なる知識を越えて、直感的で、しかも深く人間性に関わるような「思いがけない出遭い」を、本巻のページを開いて体験していただければ、それはとても素敵なことです。
──掲載作品のレイアウト・クローズアップの意図と見どころなど
本巻には、これまで美術全集で取り上げられたことのない作品を、多数掲載しました。加えて、各作品の図版レイアウトにも、大いに気を遣いました。作品の魅力を最大限に引き出すためには、本そのものも美しく魅せるものでなければならないと思ったからです。
たとえば華厳宗祖師絵伝(高山寺)には、新羅からの留学僧・義湘と唐の娘・善妙が並ぶ場面が描かれています。少しうつむく善妙の仕草に、彼女が義湘に対して抱く淡い恋心が見え隠れします。対して、稚児観音縁起絵巻(香雪美術館)には、60歳を過ぎた老僧と13.4歳の美しい少年との出遭いの場面があります。こちらでは老僧の方が、うつむき加減。少年は、この老僧にほほえみかけています。華厳宗祖師絵伝は、最終的に善妙が龍へと変身を遂げ、義湘を無事に帰国させるというお話。対して、稚児観音縁起絵巻は、実は少年は十一面観音の化身で、老僧の仏道修行を助けて往生へと導いたと結ばれます。今回、この二作品を同じページの上下段に並べて掲載しました。すると、人物の身振りや話の展開が、とてもよく似ていることは一目瞭然です。そして、さらに次ページには法然上人行状絵図(京都・知恩院)に描かれた、中国初唐時代の僧・善導と日本の鎌倉時代の僧・法然の出遭いの場面を載せました。夢の中で出逢うことにより、法然は善導に導かれて浄土信仰に専心するのです。異性愛、同胞愛、時空を越えた師弟愛…中世の僧侶たちは宗教的な深い心の繋がりを求めていたこと、あるいは、僧侶に対して人間的な心の繋がりを中世民衆は期待していたことを、こうした絵巻は垣間見せてくれるのです。法然上人行状絵図には、老若男女が法然の説法を聴こうと集まった場面がありますが、これも本巻に掲載しました。群衆一人ひとりの身振りや表情に注目していただくと、その心の内が垣間見られるようで、おもろしいと思います。
もう一つ、本巻で大いに工夫を凝らしたのは、全図と部分図との組み合わせです。
西洋のルネサンス絵画などは、一点透視図法で構図が決められているために、画面全体を見渡すことで、絵の主題や物語の展開がわかります。ところが、これに対して、わが国中世の絵画は、画面のそこかしこに細やかなモチーフを散らして描いているために、全図を一瞥しただけでは何が主題なのかよくわからない。そんな作品がたくさんあります。私たちは日本に生まれながら、西洋=近代の「まなざし」を獲得してしまっているので、日本の古い絵画の魅力を見落としてしまいがちなのです──そこで、部分図の出番です。
たとえば春日宮曼荼羅図(南市町自治会)は見開き右ページに全体図を、左ページには部分図を掲載しました。春日大社本殿の建築、春日若宮(神)と藤原氏(人)の出遭い、その若宮が普賢菩薩の姿で表れたところ──こうした部分図を全図と並べて比較しながら見てください。すると、巨視的/微視的に本作品の美しさ・細やかさを堪能することができるでしょう。まさしく「美は細部に宿る」のです。図版解説では、谷口耕生さん(奈良国立博物館)が細部の意味を丹念に読み解いてくれています。
あるいは公家列影図(京都国立博物館)は、カンノン開きページに掲載しました。これは、平安~鎌倉時代に大臣に就任した公家を並べて描いた巻子本形式の作品ですが、図版レイアウトではその形式を一旦解体することを試みました。すなわち、描かれた一人ひとりの人物をクローズアップし、それぞれの肖像を年齢順に置き直して、再構成してみたのです。すると、髭の有無、目尻のシワや白髪など、年相応の描き分けに絵師は相当気を遣っていることがわかりました。年齢差ばかりではありません。痩せた人、肥満気味の人、さらには親子同士で似ている者など、描かれた一人ひとりの個性が歴然と目前に浮かび上がってきたのです。このページは黒田智さん(金沢大学)が構成してくれたのですが、はじめてそれを見たとき、私も驚かされました。これはきっと、史料を読むとき、歴史小説を読むとき、あるいは大河ドラマの配役の良し悪しを語るときなど、今後大いに参照されることになるのではないかと思います。
──今回の巻の監修を終えて、一言お願いいたします。
本巻に掲載した部分図は、単に全図の一部を気まぐれに切り取り、抜き出し、拡大したものではありません。本巻監修の立場から、私が読者のみなさんに「この作品、この部分を、是非とも注意深く見て欲しい」と願って、とくに大きく載せたのです。つまり、そこには作品に対する私の見方・考え方が反映されています。そうした細部に注目することにより、みなさん一人ひとりが作品と向き合い、そして作品が制作された時代の視覚や精神を、見たり感じたりして欲しいのです。「私はこの絵のこの部分がおもしろいと思いました」「あなたはどうですか?」──そうした問いかけが、なされていると思っていただけたら、幸いです。すべての作品に部分図が付されているわけではありません。しかし、すべての作品について解説文は記されています。そこには全体と部分、作品そのものとそれが作られた時代状況、あるいは比較すべき(関連する)他作品についてなど、多様で細やかな情報が記述されています。解説文を執筆してくれたのは、鋭い感性と深い学識とを有する、主に若い研究者たちです。彼らの意見に同意したり、あるいは反対したりしながら読んでほしいと思います(関西風にいえば、ツッコミを入れるですね)。
本巻のページをぱらぱらとめくる。ふと目にとまった作品があれば、全体図と細部とをじっくり見る。解説文を一読し、研究者が注目するポイントを確認する。そしてまた、あらためてカラー図版に目を向ける。その繰り返しが、先に述べた「思いがけない出遭い」を、きっと豊かにものにしてくれるでしょう。
──最後に、監修者自身による、この巻の見どころをお願いします。
【第一章 絵巻物】
まず巻頭は『平治物語絵巻』(静嘉堂文庫美術館)。ここでは貴族が上座に、武士たちは下座に位置しています。中世は確かに武士が政治や経済の実権を掌握し、歴史の表舞台に立った時代でした。しかし建前上、武士は天皇や公家を立てることにより、社会を動かしていたのです。この場面には、そうした当時の権力構造が座る位置によって象徴的に表わされています。けれども、よく見ると、下座にいる武士は身を乗り出し、対して、上座にいる貴族は腰が引けている。ここでは社会的な建前と心の中の本音とのズレも、身振りによって描き出されているのです。さらに続く『絵師草紙』(宮内庁三の丸尚蔵館)『東北院職人歌合絵巻』(東京国立博物館)『三十二番職人歌合絵巻』(サントリー美術館)では、天皇や公家あるいは武士でもない、さまざまな身分・職種の人たちが中世という時代を動かしていたことを見せてくれます。
【第二章 掛幅説話画と古絵図】
『六道絵』(聖衆来迎寺)は鎌倉時代に制作された掛幅形式の説話画の傑作で、国宝に指定されています。なんといっても、15幅セットという大作です。本巻には15幅すべて、それに部分図も掲載しました。六道とは地獄・餓鬼・畜生・阿修羅・人・天の六つの世界のこと。本作品は中世の人たちが思い描いた仏教の宇宙観を主題とします。『日本美術全集』第14巻「若冲・応挙・みやこの奇想」には伊藤若冲筆「動植綵絵」(宮内庁三の丸尚蔵館)30幅、第16巻「幕末から明治時代前期」には狩野一信筆「五百羅漢図」(増上寺)100幅が収録されています。こうした大作をぜんぶ並べてみることは、展覧会でもなかなか難しい。それは『日本美術全集』を広げたときだけに得られる喜びだと思います。壮観です。また、『葛川与伊香立庄相論絵図』(葛川明王院)や『播磨国鵤荘絵図』(法隆寺)などの地図は、これまで美術とはみなされてきませんでしたが、あらためて絵画として眺めてみると美しい。これらは制作当時の人々が生きた空間、身近に感じた地域の在り方を今を生きる私たちに伝えてくれます。
【第三章 人の姿かたち】
伝源頼朝像・伝平重盛像・伝藤原光能像(神護寺)は、近年の研究成果を踏まえて、足利直義像・足利尊氏像・足利義詮像である可能性を指摘しつつ掲載しました。描かれたのは誰か? という「謎解き」も知的好奇心を誘いますが、一人ひとりがたいへん美しく描写されていることに感覚的に驚くことも大切です。強さよりも美麗さを、これを描いた絵師(これを描かせた注文主)は求めていたことがうかがえます。それに比べて、『公家列影図』(京都国立博物館)に描かれた公家たちの面立ちは、マンガみたいで面白い。美しさよりもユニークさ(個性)を際立たせた描写です。
【第四章 仏画と垂迹画】
「多宝塔柱絵」(石山寺)、「大威徳転法輪曼荼羅図」(個人蔵)、「仏涅槃図」(九州国立博物館)、「春日宮曼荼羅図」(南市町自治会)は1990~2000年代に相次いで発見された作品で、研究論文や展覧会図録等を除くと、今回はじめて大判のカラー写真を書籍に掲載、新たな知見を盛り込んだ解説をつけて紹介します。また「普賢十羅刹女像」(奈良国立博物館)、「熊野権現影向図」(檀王法林寺)は以前から知られていた名品ですが、どちらも1998年度に修復がなされて、画面がとてもきれいになりました。今回、修理後の写真を掲載しています。
【第五章 書と工芸】
後白河・後鳥羽・後宇多・後醍醐──いずれも、この時代を代表する天皇です。彼らゆかりの神護寺・水無瀬神宮・大覚寺・四天王寺には、それぞれの手形が押された文書が遺されています。朱で染められた手の跡(手印)は、一人ひとりの身体を、生々しく現在に伝えます。また神社に奉納された甲冑や馬具は武士の美意識と信仰心を、仏舎利を納めた舎利容器の荘厳は仏陀に対する真摯な崇敬の念を、目に見えるかたちで今に伝えてくれる遺品です。
このインタヴューの冒頭で、私は子どもの頃の「見ること」の孤独について語りました。しかし、今は違います。本巻をより良いものとするために、編集の清水芳郎さん、河内真人さん、藤原えりみさん、藤田麻希さんはじめ多くの人たちが力を尽くして下さいました。私たちは忌憚なく意見交換し、ときには衝突もしながら、真心込めて本巻をつくりました。仕事を通じて、私にも新しい友達ができました。そして、もしもあなたが本巻を開いてくださったなら、私は一緒に作品を前にして語り合える友人をさらにたくさん得られる予感がするのです。これもまた「思いがけない出遭い」です。それは、とても喜ばしいことです。本巻を無事刊行することができて、ほんとうに良かった。ありがとうございました。
(編集担当・河内真人)
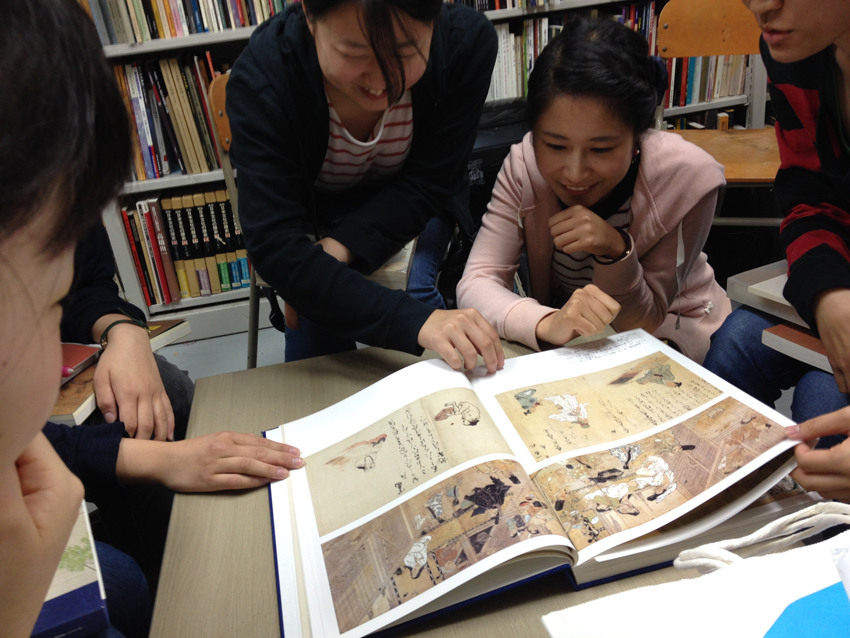
『中世絵巻と肖像画』をめくる奈良女子大学・加須屋ゼミの学生