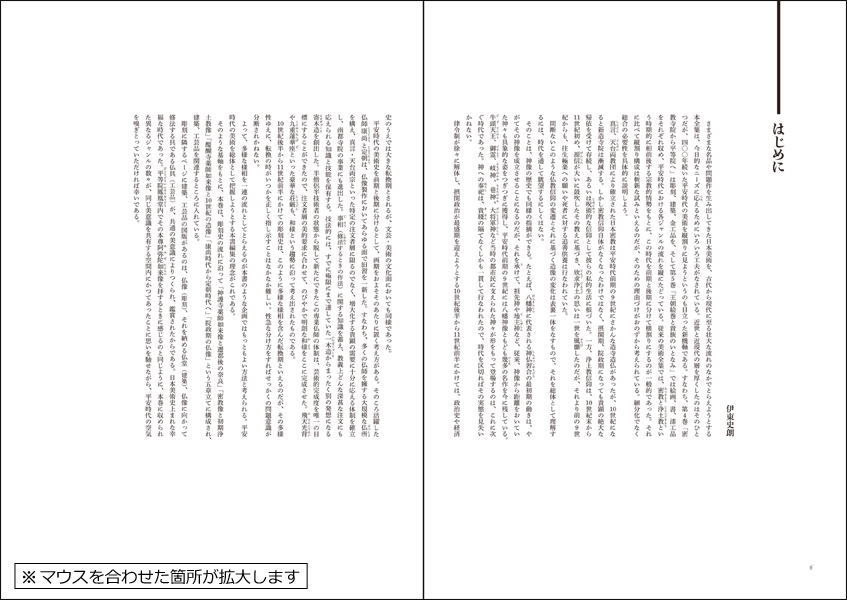日本の心が紡いできた比類なき「美」。「日本美術全集 全20巻」。今、日本に存在する「最高の美」のすべてがここに。
第13回配本 密教寺院から平等院へ(平安時代Ⅰ)
| 責任編集/ | 伊東史朗(和歌山県立博物館館長) |
|---|---|
| 定価 | 本体15,000円+税 |
| ISBN | 9784096011041 |
| 判型・仕組 | B4判/304頁 カラー図版口絵144ページ・カラー図版両観音16ページ モノクロ解説ページ144ページ/上製・函入り/月報付き |
もくじ
- はじめに 伊東史朗(和歌山県立博物館館長)
- 平等院阿弥陀如来像に至る仏像史とその技法 伊東史朗(和歌山県立博物館館長)
- 密教絵画から彫刻へ──曼荼羅・図像の請来と彫像化 佐々木守俊(岡山大学准教授)
- 浄土の造形──阿弥陀浄土を中心に 武笠 朗(実践女子大学教授)
- 八幡神像の成立 伊東史朗(和歌山県立博物館館長)
- コラム/平安時代前期の国家と仏像 皿井 舞(東京文化財研究所 主任研究員)
- コラム/密教法具について 関根俊一(奈良大学教授)
- コラム/専業仏師の出現 根立研介(京都大学教授)
- コラム/平等院鳳凰堂の特質 上野勝久(文化庁 文化財部参事官)
概要
794年、新しい都・平安京が定められ、都の入り口に官寺として建立された東寺が、唐から密教をもちかえった空海に与えられます。以後、都とその周辺で造寺・造仏がさかんに行なわれるようになりました。厳しいまなざしの神護寺の薬師如来立像をはじめ、室生寺の十一面観音菩薩立像や醍醐寺の聖観音菩薩立像など平安時代前期を代表的する仏像にはじまり、東寺講堂で立体曼荼羅を構成する諸像や、地方の寺院の像なども取り上げます。10世紀になると、寺院造立が漸減していきますが、その間も密教信仰は貴族たちの信仰として根付いていました。そして、摂関政治が最盛期を迎える10世紀後半、末法の世をまえに浄土教信仰が興隆し、摂関家をはじめとする貴族が競って大寺院を建立します。それら寺院に納められる仏像の製作のために、康朝や定朝ら仏師も大規模な仏所を構え、その需要に応えるようになりました。この時期に製作されたのが、同聚院の不動明王坐像や平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像です。平安時代400年の間に各地でつくられた仏像をおよそ200体。いっぽうで在来の神との融合が行なわれた、いわゆる神仏習合による八幡神像など、仏教の影響を受けて造像されるようになった神像も多数紹介します。あわせて、仏像が収められた建築、荘厳具なども取り上げています。
第一章 神護寺薬師如来像と遷都後の奈良
空海に関わる造像を中心に、平安時代初期の密教寺院の仏像と、神仏習合による神像を取り上げました。神護寺薬師如来立像、室生寺薬師如来立像、向源寺十一面観音立像、松尾大社三神像など。
第二章 密教像と初期浄土教像
東寺講堂をはじめ、観心寺如意輪観音菩薩坐像、南院不動明王立像など、9世紀前半に造像された仏像を取り上げました。このころから製作されるようになったと考えられる獅子狛犬の像も紹介します。
第三章 醍醐寺薬師如来像と10世紀の造像
9世紀末から伽藍が整備されはじめた醍醐寺ほか、神護寺普賢菩薩坐像や清凉寺兜跋毘沙門天立像など、都とその周辺に残される仏像と、八幡神などの神像を取り上げました。
第四章 康尚時代から定朝時代へ
仏像が彫り出される木材が1本の材を使う一木造から複数の材を矧いで用いる寄木造となり、またこれまで残されていなかった製作者の名まえが判明するようにもなります。同聚院不動明王坐像、平等院阿弥陀如来坐像・雲中供養菩薩像、六波羅蜜寺地蔵菩薩立像などを取り上げました。
第五章 院政期の仏像
10世紀以降の浄土教の興隆にともない造像された阿弥陀如来を中心に取り上げます。また、都から離れた各地の寺社に残される、臼杵磨崖仏や三佛寺不動明王立像、江原浅間神社浅間神像などのほか、舞楽面や密教法具、建造物を紹介します。
(編集担当・一坪泰博)
少しばかり仏像には思い入れがあるところにこの巻を担当できたことは、仏さまのお導きだと思いました。しかも、ご覧いただくとおわかりいただけますが、ほかの仏像を中心とした巻とくらべると「仏像率」が高いです。仏像以外に掲載したのは、建築が十数点、ほかに密教法具や梵鐘などが数点のみで、残りのページはすべて仏像と神像、そして舞楽面です。平安京遷都から鎌倉幕府成立まで、およそ400年間に造像された200体ほどを詰め込みました。その作業をされたのが、本巻代表執筆者の伊東史朗先生です。
伊東先生のような仏像研究者(正確には彫刻史研究者でしょうか)は、いったい仏像のどんなことを研究されるのだろうかということについて、じつは仮想していませんでした。きれいだ、美しい、奈良時代と平安時代のお顔はだいたいわかる、というくらい。ゆえに、とあるお堂での撮影のさい、仏像をひっくり返して中身にライトを照射したり……そんなことをするとはほんとうに驚きました。割れを防ぐために仏像の中を空洞にすることが多いとは知識としてはありましたが、実見するのははじめてで、畏れおおすぎて遠巻きにしました。そんなことをするときっとバチが当たるにちがいない。
さて、伊東先生は、はじめにこの倍くらいの数の仏像を候補に挙げられました。もとになる仏像、それらの派生、地方性など、いろいろお考えのうえでの選択だったと思いますが、それでは昆虫図鑑みたいになってしまうので、大幅に削っていただいたわけですが、わたしでも「惜しい」と思った像が多くあり、心残りです。伊東先生はとても寡黙な方で、余計なことは話しません。話さないだけでなく、メールでも「それでよい」だけで、「ダメ」なことは返事さえくれない、まったく無駄なことは省かれます。仏像と対峙する修行僧のような感じがしました。だから掲載した仏像はだいたい正面を向いています。それから、後補(後世に補ったということ)の持物や光背などが、なるべく写っていない写真を選びました。背景はほんの薄いグレーが理想です。余計なものは入っていません。
仏像研究者ではないわたしたちは、どのように仏像と対峙すればよいでしょうか? 写真でみたことのある仏像をもとめて、じっさいのお堂のなかで拝むのがいちばんよいと思いますが、展覧会場で拝むのもまたべつの感動があります。ライティングももちろんですが、ちょっとみせてね、と背中側にまわれることも、わたしは楽しみにしてます。そして、今回のように誰かが撮った写真(プロの写真家によるものがほとんどです)を何百と並べてみられるのは、またまたべつの楽しみがあるでしょう。日本において仏像が被写体とされてからまだ140年ほどにしかなりませんが、アングルなどはすでに定型化がなされているようです。それでも写真家がその仏像をどのように切り取るか、そこには被写体が仏像ゆえの思い入れがあり、それを編集者が汲み取って……ということになるのだと思いますが、今回はその点で比較的フラットな写真が多いと思います。それは伊東先生の研究態度であるとともに、「日本の美」の解放というと大仰ですが、もっと自由に自分の好きな仏像を探してみてはどうでしょうか、という提案ではないかと勝手に思っています。
ちなみに、仏像は「みる」のではなく「拝む」としたほうがよいです。お寺さん(ご住職ほかお寺の関係者)のまえで「仏像をみせてください」と云うと「拝んでください」と叱られます。とある小さなお寺に拝観をお願いしたとき、「あなたはちゃんとわかっているのでヨシ」とお許しを得たことがあります。だいたいは「見せて」と云ってくるので「断わる!」そうです。
ところで、本を作っていく過程では膨大な反古紙が出ます。レイアウト案にはじまり、文字の校正、色の校正、図版の差し替えを何度も重ねるあいだに何百何千と捨てなくてはならない紙が出るのですが、今回これらの紙にいちいち仏像が印刷されていたのが苦痛でした。そもそも文字が書かれた紙をまるめて捨てるのも気が引けるような感じで、くり返すうちに絵画や建築物の写真などまでは気にならなくなりましたが、仏像はどうしても慣れませんでした。いちいち「どんど焼き」に持ち込むわけにもいかないので、サッと知らぬフリをして捨ててきたわけですが、仏さまにはすべてお見通しだろうと、モヤモヤしたままこの年の瀬を越さなくてはなりません。
(編集担当・一坪泰博)