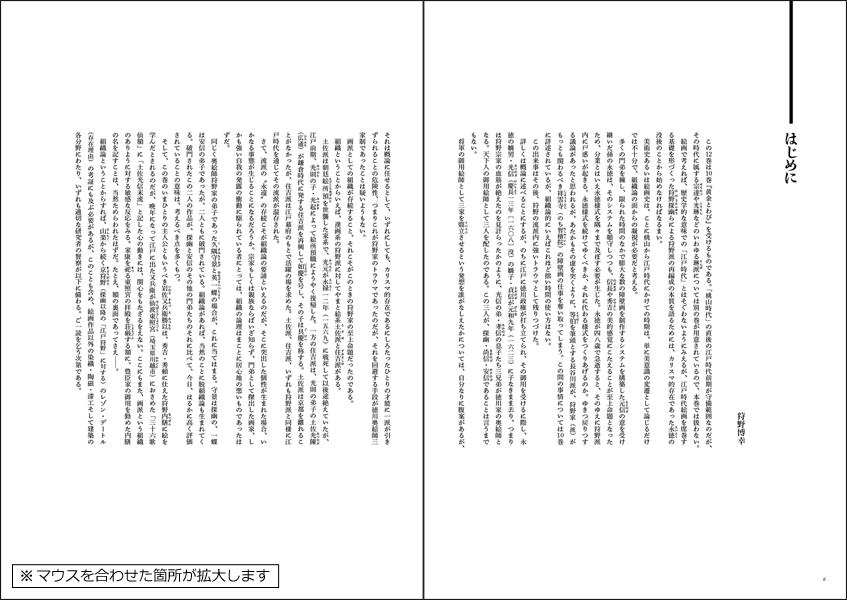日本の心が紡いできた比類なき「美」。「日本美術全集 全20巻」。今、日本に存在する「最高の美」のすべてがここに。
第9回配本 狩野派と遊楽図(江戸時代Ⅰ)
| 責任編集/ | 狩野博幸(同志社大学教授) |
|---|---|
| 定価 | 本体15,000円+税 |
| ISBN | 9784096011126 |
| 判型・仕組 | B4判/288 頁 カラー図版口絵144ページ・カラー図版両観音16ページ モノクロ解説ページ128ページ/上製・函入り/各巻月報付き |
もくじ
- はじめに 狩野博幸(同志社大学教授)
- 江戸前期画壇を貫道するもの 狩野博幸(同志社大学教授)
- 狩野山雪の知られざる一面――晩年の投獄をめぐって 五十嵐公一(兵庫県立歴史博物館)
- 将軍御成の「しつらい」について――柳営御物絵画の和物への傾斜 矢野 環(同志社大学教授)
- 慶長小袖から寛文小袖へ――17世紀服飾史における劇的な変化 丸山伸彦(武蔵大学教授)
- 二条城と日光東照宮 伊東龍一(熊本大学教授)
- コラム/風俗画の情報の探り方――『色道大鏡』を一例に 狩野博幸(同志社大学教授)
概要
『日本美術全集』第12巻は、時代別では「江戸時代Ⅰ」にあたり、タイトルは『狩野派と遊楽図』です。あつかっている時代は、桃山時代の狩野永徳以降から、17世紀後半、師宣、春信らによる浮世絵誕生前夜までにあたります。
さて、信長、秀吉の寵愛を受け、天下国家の絵師として活躍した永徳が1590年、48歳で急逝したとき、狩野派内部で生き残りをかけた戦略が施されます。政権の帰趨が判然としないなかでさまざまな可能性に対応した、したたかで巧みな策はやがて実を結び、新たに徳川が支配する世で狩野派は画壇を支配していきます。
責任編集の同志社大学狩野博幸先生は、時代への洞察をもとに、狩野家存亡をかけた戦略を、美意識の変遷としてではなく組織論としてとらえ、読み応えのある論を展開しています。
狩野派を軸に据え、そこからはみ出してゆく久隅守景・英一蝶、また、時代を活写した風俗画、さらには風俗画の傑作を数々ものし、浮世絵を準備したとも評される岩佐又兵衛……。江戸前期画壇を一望する、華やかさに満ちた一巻です。
注目点
1.探幽はもちろん、近年評価が高まる山楽・山雪ら京狩野の作品をたっぷりと紹介
永徳没後、巧みな戦略で生き残り、狩野派宗家を担った狩野探幽の代表的な作品はもとより、近年改めて作品の評価が高まりつつある狩野山楽・山雪の作品を、昨年度の大規模な展覧会の実績を踏まえて、これまでの全集では考えられないほどに、大々的に紹介しています。
2.泰平の世を活写した風俗画の傑作を、新出作品を含めて網羅
狩野派の画業の訓練のたまものとして多く描かれた『洛中洛外図屏風』も、前時代の「上杉本」以降の主要なものを紹介し、さらに泰平の世を謳歌する民の生き様を活写し、浮世絵前夜のこの時期に傑作が排出した遊楽図を中心とした「風俗画」(たとえば、『湯女図』『四条河原遊楽図』『彦根屏風』など)も本巻にたっぷり収録しています。また、本巻で初めて紹介する、狩野孝信の手になる新出の『北野社頭遊楽図屏風』もたいへん魅力的な作品です。
3.狩野派に学んで、のちに個性を発揮する久隅守景・英一蝶も本巻で
狩野派に学びながら、やがて狩野派から離れて活躍する守景と一蝶。かたや国宝『夕顔棚納涼図』で、かたや重文の『布晒舞図』や『吉原風俗図巻』で今日つとに知られる二人の画家は、破門というかたちで狩野派と袂を分かった共通点をもちますが、組織の存続とそこからはみ出してゆく才能ある個性という文脈で眺めると残された作品に一層の興味が湧いてきます。
4.本巻のもうひとりの主役は岩佐又兵衛
本年度の大河ドラマ「黒田官兵衛」にも登場する戦国武将・荒木村重の子息であったとされる岩佐又兵衛は、信長の粛正を逃れ、一族・郎党でひとり生き残ったことが生涯のトラウマとなり、『山中常磐物語絵巻』『堀江物語絵巻』などの作品にそれが色濃く反映しているといわれます。いっぽうで、近年、作者として改めて同定された『洛中洛外図屏風 舟木本』や『豊国祭礼図屏風』など、生き生きとした群像表現に巧みな画術を駆使し、数多くの風俗画の傑作を残しており、この時代を代表する画家として又兵衛を取り上げています。
5.絵画以外の染織・工芸・建築も網羅
風俗画において華やかな場面を飾る人々の「きもの」にも自然と目が向きますが、今に伝わるこの時代のきものを取り上げ、慶長から寛文において劇的に変化する染織の実相を実物と論考から探ります。また、色絵をはじめ、やはり華やかさを増すやきもの、初音の調度に代表される工芸の粋も本巻に収載しています。
さらに、この時代の代表的な建築物である二条城と日光東照宮は、図版で詳細にお見せするのはもちろん、論考においても構造の変遷という視点から建築史的位置づけを試みています。
(編集担当・清水芳郎)
空想美術館としての美術全集
美術作品を愛でるのには、仏像のように寺に出向いて像と向き合う以外は、少々乱暴に大別すると、美術館で作品を鑑賞するか、本シリーズのような美術全集を活用するかということになるのではないでしょうか。さて、美術展は作品が実際に並ばないことには成立しませんが、美術全集ならば、実際の作品がなくとも、いわば空想美術館のように好きな作品を選定して、その図版を掲載し、思うがままに理想的なラインナップで構成できると思われるかもしれませんが、全集には全集なりのいくつかの問題点があります。
美術撮影はフィルムありき
その巻のテーマに沿ってまず作品を選定する作業がまず必要ですが、この点についても、作品の洗い出し、編集委員の先生方との議論など、さまざまな作業を伴いますが、ここではこの作業はすでに終えたこととしてお話ししましょう。
作品を本のページにきちんと印刷し、できる限り本物の作品に向き合うかのごとく紙面に再現するには、選んだ作品が写された写真を探すことから始まります。所蔵元、たとえば東京国立博物館所蔵の作品ならば、まず当該博物館に、本の趣旨を説明し、掲載許可をもらい、フィルムの貸出し願い書を提出します。美術館レベルの所蔵元ならば、このような作業をする専門のセクションなり担当の方が決まっており、このやりとりはスムーズに進みますが、さて、「写真は」という段で、大概、一悶着というと言い過ぎですが、やりとりが伴います。それは、まず、先方がもっている作品イメージが、どのようなものかという話から始めなくてはなりません。昨今、観光地でも皆さん撮影するならばカメラかといえば、「カシャ」という音とともに携帯電話ということがままあります。旧式のフィルムカメラなどめっきり見なくなり、写真はデジタル全盛といいますか、画像はデータが当たり前、下手をすれば「フィルムって何」といわれかねない状況ですが、美術作品を撮影したイメージは、まだまだ「フィルム」が重宝される世界です。
デジタルVS.フィルムともいえない作品再現
この稿をお読みの方の中にも、フィルムカメラといえば35ミリネガカラーフィルムで家族写真などを楽しまれた経験のある方はおいでになるかと思いますが、美術作品の撮影は大判カメラ、最低でもブローニーサイズのフィルム、通常は4×5(「しのご」と呼ばれる、横4インチ、縦5インチサイズのフィルム)、さらにまれにその4倍の膜面面積となる8×10(なぜか「ばいてん」と呼ばれる、横8インチ、縦10インチのフィルム)を用いての撮影が必要です(しかも、いずれも像がそのまま見える「ポジフィルム」です)。いかに印刷技術が進歩しても、この印刷の元となる写真イメージが良くなければ、作品再現にも限界があります。ですから、編集担当者はなるべくよりよいイメージ再現が可能な画像を探すことになるのです。「8×10」のフィルムがあれば理想的ですが、撮影にさまざまな困難が伴うため、このサイズのフィルムイメージがある作品はなかなかありません。また、本全集のように、片ページでB4サイズ、見開きにすればB3サイズになる判型の大きな書物ですと、標準のフィルムは4×5サイズとなります。
しかも、この12巻に収載している六曲一双の屏風ならば、フィルムは何枚になるかといいますと、通常は、屏風の撮影は2扇ずつ撮影しますので、たとえば図版番号11番の妙心寺の『龍虎図屏風』ならば、4×5フィルムを6枚借りて、3枚ずつつなぎ合わせて、ページ上に作品を再現しています(空想美術館を作り上げるにも様々な手順と印刷技術の裏付けが必要なのがおわかりいただけるかと思います)。
と、フィルムがまだまだ幅をきかせている背景をご説明しましたが、一般の写真状況と同様、ここのところ伸してきた「デジタルイメージ」についてもお話ししておきましょう。最近フィルムメーカーがフィルム生産を次々に中止して、銘柄を絞ってきていることもあり、撮影者もそろそろデジタルに鞍替えすることが多くなり、美術撮影の分野でも、デジタルイメージでのやりとりが多くなってきました。ついこの間までデジタルデータといえば、ページに比して容量が足りないとか、なにか一色足りないような痩せたイメージだとか、平面作品でも絵の奥行きの表現が物足りないとか、われわれレベルでは様々な不満があって、デジタルイメージはできるだけ使用しないようなところもありました。ただし、この分野も日進月歩で、いまや国宝級の「お経」の複製も作れる「一億画素」のプロ用機材もある時代です。肉眼では見えないくらいの画家の細かな筆致まできっちりと再現するにはデジタルカメラにしかできない芸当という場面も出てきました。
ですから、美術全集クラスの印刷になりますと、さまざまな写真イメージから、理想的な、写真を探すことが本という最終到達点をよりよいものにするために必要不可欠な大きな仕事になります。
最後は印刷の再現性
フィルム、デジタルと相対するようなもの言いをしましたが、実際は、印刷効果を鑑みて、時に印刷テストを繰り返して、使用イメージを決めます。観音ページのように大きな見開きでは、余計気を遣うことになります。また、本巻のように絵に用いられている「金」に様々なバリエーションがある場合は、金の表現と全体のバランスを見て、使用するイメージを決めることが肝要になります。
また、写真の発達史のようなお話しもしましたので、あたかも最新のフィルムであれ、デジタルデータであれ、撮影日時が最新のものがいちばん良質のイメージと受け止められたかもしれませんが、ことはそう単純ではありません。30年前に理想的な環境で撮影されたオリジナルのポジフィルムが、最新のデジタル撮影に勝る印刷効果をもたらすことがままあります。この巻にも、本巻の為に撮影した新撮フィルム、1億画素の新撮データから、それこそ30年以上前に撮影したフィルムまで、いろいろな撮影イメージを用いて、これこそが該当作品再現には最良と思われるものを様々利用して、カラーページを構成しています。
最新の印刷技術を用いて、なんども色校正を経ておりますから、一見したところ、どのようなイメージを使っているかはおわかりにはならないかと思いますが、参考までに背景のお話しをいたしました。フィルムの問題、デジタルについては、まだまだいろいろとお話しはありますが、今回はイメージ再現の裏事情に限ってお話しいたしました。
さて、ひとつの作品を借りてきて並べる以上の労力と申し上げるつもりはありませんが、見開きのカラーページをお楽しみいただく際に、空想美術館にもそれなりの時間と労力がかかっているのだなと少し思っていただければと、裏のお話しをいたしました。
どうぞ、引き続き「日本美術全集」をよろしくお願いいたします。
(編集担当・清水芳郎)