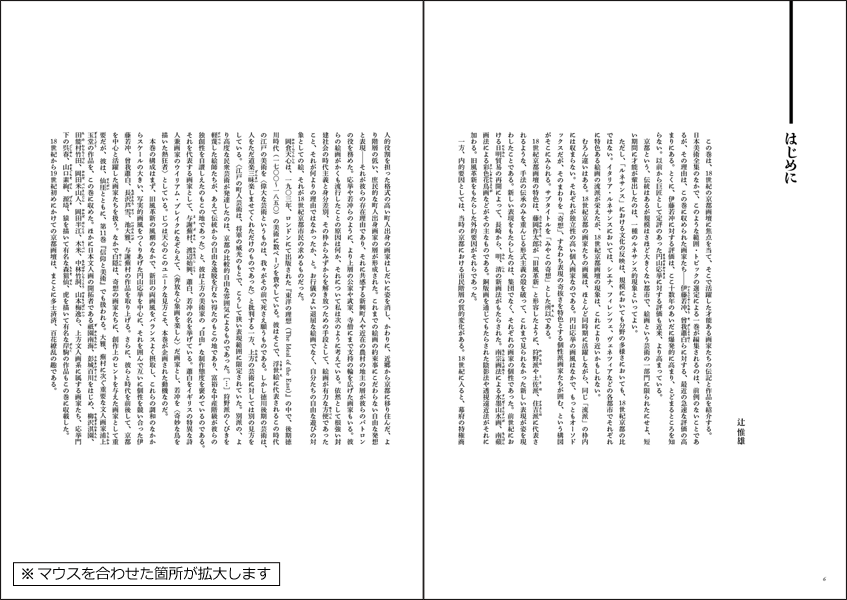日本の心が紡いできた比類なき「美」。「日本美術全集 全20巻」。今、日本に存在する「最高の美」のすべてがここに。
第2回配本 若冲・応挙、みやこの奇想(江戸時代Ⅲ)
| 責任編集/ | 辻 惟雄(東京大学名誉教授) |
|---|---|
| 定価 | 本体15,000円+税 |
| ISBN | 9784096011140 |
| 判型・仕組 | B4判/288 頁 カラー図版口絵144ページ・カラー図版両観音16ページ モノクロ解説ページ128ページ/上製・函入り/各巻月報付き |
もくじ
- はじめに 辻 惟雄(東京大学名誉教授)
- ミヤコに奇想横溢――18世紀の京都画壇 辻 惟雄(東京大学名誉教授)
- 伊藤若冲 生涯と画業 岡田秀之(MIHO MUSEUM学芸員)
- 応挙の力、芦雪の奇 金子信久(府中市美術館学芸員)
- せめぎあい、継承する、日本の文人画――関西を中心に 安永拓世(和歌山県立博物館学芸員)
- コラム/若冲『動植綵絵』の妙技――生命の美しさの表現追求 太田 彩(宮内庁三の丸尚蔵館学芸室主任研究官)
- コラム/江戸時代後期の書――髙橋利郎(大東文化大学准教授)
概要
『日本美術全集』第2回配本は、「若冲・応挙、みやこの奇想」と題した巻で、伊藤若冲を中心に18世紀の京都で活躍した円山応挙、曾我蕭白、長沢芦雪といった画家の作品を軸に紹介しています。「日本のルネサンス」にもたとえられる、個性的な画家を次々と排出した、江戸時代でもひときわ華やかな時代の、表現の奇抜さを特色とする画家たちの作品をたっぷりとご紹介します。
注目点
1. 伊藤若冲の最高傑作、『動植綵絵』を高精細で完全収載。
展覧会でも、めったに一堂に会することのない『動植綵絵』全三〇幅を完全収載。しかも本全集の14巻に収載した『動植綵絵』の画像は、修復後の絵を一幅一幅、最新鋭の撮影技術を駆使して撮影した画像を収載しています。通常は大判のフィルム1枚で一幅を撮影しますが、今回のものは18分割でデジタル撮影し、それをつなぎあわせた画像ですので、細部まで緻密に再現することが可能になりました。
2. 若冲を中心に、「奇想の画家」の主要作品を網羅
従来の美術全集では、せいぜい4〜5点しか収載されてこなかった伊藤若冲作品ですが、本全集では43点も収載しているのをはじめ、円山応挙、曾我蕭白、長沢芦雪といった展覧会が開かれれば多くの鑑賞者を集める、いわゆる「奇想の画家」の主要作品を網羅し、作品の魅力に画像・論考の両面から迫り、今を生きる私たちの注目をなぜ集めるのか、その背景にある“絵の力”について、紹介しています。
3. 文人画の系譜を位置付ける
江戸時代の中期〜後期にかけて、中国の影響のもと、日本に華開く「文人画」の系譜を丁寧にたどり、関西を中心とした画家たち、池 大雅、与謝蕪村、浦上玉堂、岡田米山人といった画家たちの作品を大画面で紹介しています。
4. 論考は「ミヤコに奇想横溢」
本巻監修者は、日本美術界の重鎮、辻 惟雄先生。若冲、蕭白、芦雪といった、今日の日本美術の展覧会の中心を成す画家たちにいち早く注目し、若冲ブームに先鞭を付けた当事者でもあります。辻先生の論考では、18世紀の京都に「奇想の画家たち」が数多く登場した背景を探り、並び立つ個性的な画家たちの画風を見事に関連づけて語っています。当時、政治の中心は江戸に移ったものの、美術の中心は京にありと、生き生きとした様相を活写しています。
5. これまでにない構成
とかく江戸時代の文化は大きく分けて、17世紀末の大坂を中心とした元禄文化と、19世紀の江戸を中心とした文化文政期の文化に分けがちですが、こと美術に関して言えば、18世紀の京都にはそうした浅薄な理解を超えた文化が育ち、華開いたのです。この巻の責任編集の辻 惟雄先生は18世紀の京都画壇を西洋のルネサンスに比して、「日本のルネサンス」と称しています。西洋のルネサンスは文芸や思想などさまざまな分野で大輪の花が開いた一方で、日本ではおもに美術に限られたことでしたが、この巻を通じて美術の華開くさまをこれまでにない魅力的な一巻で十二分に紹介しています。
(編集担当・清水芳郎)
若冲は一日にして成らず
14巻は、伊藤若冲という絵師が大きくクローズアップされた巻になりました。今でこそ、誰も「いとうじゃくちゅう」という名前を読み間違えることはなくなりましたが、2000年に京都で「没後200年 若冲」展が開かれる直前、小学館で若冲筆『動植綵絵』を紹介する本の企画書を持って社内を回ったときには、何人かが、「いとうわかおき」って誰なの?という案配でした。
若冲の代表作といえば、宮内庁三の丸尚蔵館が所蔵する『動植綵絵』全三〇幅があります。一幅が畳一枚くらいの大ぶりの作品で、三〇幅が一堂に展覧されることはあまりありませんが、2000年代になって三回、そうした機会に恵まれました。初めが2007年に京都の相国寺承天閣美術館で、次いで2009年には東京国立博物館の「皇室の名宝」展で、さらに2012年には桜植樹100年を記念して、アメリカのワシントンナショナルギャラリーにおいて、『動植綵絵』が三〇幅並ぶ展覧会が開かれました。
では、2007年より以前に三〇幅が並んだのはいつかと調べてみますと、じつは大正15年のことになります。
ことほど左様に、伊藤若冲が注目を集め、再評価されるようになったのは、近年になってからのことです。
では、そのきっかけはといえば、1968年から雑誌『美術手帖』で始まった辻惟雄先生(第14巻の監修者でもあります)の連載「奇想の系譜」においてでした。この連載は、辻先生が、伊藤若冲をはじめ、曾我蕭白、長沢芦雪、岩佐又兵衛といった、一時期は忘れられていた江戸時代のユニークな画家たちを毎号取り上げ、このまま忘れ去られていくのはもったいないとして、現代に通じる絵の奇抜さ・面白さを論じたものでした。
のちに、『奇想の系譜』として1冊の本にまとまり、追随する多くの研究者を生み、また、現代美術家の村上隆氏をはじめ芸術家にも大きな影響を与えました。そして、この本をきっかけとして江戸時代の画家たちにも目が向けられる時代を迎えるようになりました。
今から46年前に刊行された『原色日本の美術』でも、22年前に講談社から出された美術全集でも伊藤若冲の絵は4点しか掲載されていませんが、今回の全集にはなんと43点もの若冲作品を掲載していますから、隔世の感があります。
代表作『動植綵絵』
『動植綵絵』は、若冲が42歳くらいから、ほぼ10年の歳月をかけて描き、両親、弟とみずからの永代供養を願って、相国寺に寄進した作品です。
三〇幅に描かれている、数多くの鳥や魚、植物などの動植物の絵の背景には、仏教的な思想が込められているといわれています。仏教には「草木国土悉皆成仏」という考えがあり、生きとし生けるものすべてに仏性をみるという捉え方をします。
『動植綵絵』には生きるものすべてを描ききろうという意欲が感じられます。また、相国寺に寄進する際には三〇幅と『釈迦三尊像』三幅がセットになっていました。相国寺では釈迦三尊像を中心にして、15幅ずつ左右にわけて、お堂にかけるようにして法要を行なっていたそうです。ですから『動植綵絵』を、単にテクニックに優れた美しい絵として捉えるのでなく、壮大な仏画であると論じる見方が強くあります。
この『動植綵絵』ですが、平成11年から16年にかけて、大規模な修復が行われました。絹地の裏まで剥がして修復したので、それまで知られていなかった若冲の絵の技法も明らかになりました。
若冲の緻密な絵は、動植物が重なりあうように描かれた絵でも、絵具はどこも重ならず、厳密な下絵を元に描かれていることは表から見てもわかりますが、裏を剥がして検証したことで、中世の仏画などに用いられた裏彩色という技法を若冲が効果的に用いていたことが明らかになりました。絹地の裏からも色を入れることで、表から見たときに、その部分の色が強く感じられます。そして、若冲は、ほぼ全幅でこの効果を活用していることが判明しました。
このように、絵画技法に習熟しながら、昔ながらの技法もきちんと消化して、最大限の効果をわかってやっているわけです。そのうえ高価な絵具をふんだんに使っているので、ほかの画家にはなかなか真似ができません。若冲の贋作が時々出てきますが、絵の濃密な印象から、さぞや絵の具を厚塗りしているのだろうと、贋作も厚塗りのものが多いのですが、若冲の真筆はごくごくうす塗りで仕上げているのです。
さて、本全集の14巻に全三〇福を収載した『動植綵絵』については、修復後の絵を一幅一幅、最新鋭の撮影技術を駆使して撮影した画像を収載しています。通常は大判のフィルム1枚で一幅を撮影しますが、今回のものは、デジタルカメラで18分割で撮影し、それをつなぎあわせた画像ですので、細部まで驚くほど緻密に再現することが可能になりました。
この画像は宮内庁三の丸尚蔵館と東京文化財研究所が共同で管理していて、二年前にやはり小学館から刊行した豪華本を除けば、今回の全集に初めて掲載されています。
先にも申しましたように、三〇幅が一堂に会する機会はこの先も多くは望めませんので、本全集で好きなときに三〇幅をご堪能いただければと思います。
伊藤若冲とはどのような画家だったのか
若冲の人となりについて、ご説明しましょう。京都・錦小路の青物問屋「桝源」の四代目の跡取りとして生まれた伊藤若冲は、もともとはプロの絵師ではありませんでした。青物問屋は宮中にも野菜を卸す、いわば野菜の商社のようなものですから、とても裕福でした。若冲は23歳のとき、父親の死をきっかけに家督を継ぎますが、画家への思い断ちがたく、40歳で次弟に家督を譲り、画家を目指します。絵の修業は、初めは狩野派の画家について学んだといわれています。しかし、狩野派は粉本主義といわれる、お手本をひたすら模写する教育方法をとっていたために、江戸時代中期になると画家の個性が薄れていきます。そのころ、中国から宋元画といわれる細密な絵が入ってきましたので、若冲はそれを模写しながら学んでいたようで、そのころの模写を基にした作品も残っています。
こうして、自分の画風を確立していくいっぽう、自分は見たものしか描けないということで、庭に鶏を十数羽飼って、その生態を観察しながら自分の絵を深めていったというのは有名な話です。
同時代の円山応挙も写生を極めていきますが、若冲の写生は現実を突き詰めていくことで幻想に至ってしまうような独特のすごさがあります。
当時、大坂に木村蒹葭堂が主宰するサロンのような集まりがあり、博物画や貝の標本など、博物学的なものが集まっていました。若冲はそこに出入りをしてそれらを実見して、自分の絵に生かしていたようです。また、若冲の絵は写実的にも優れていますが、それらをどう組み合わせて画面を成り立たせるかという構成力が抜群に上手いのです。
白い象を中心に据えた有名な『鳥獣花木図屏風』もいってみれば仏画だという研究者がいます。象は普賢菩薩が乗る動物だとか、やはり動物と鳥をとにかく多くの種類を描き込もうという姿勢からも、『動植綵絵』に繋がる仏画的な世界が感じられます。当時の禅宗の僧から多大な影響を受けていた若冲の絵画の背景には現代を生きる私たちがうかがい知ることができないほどの仏教的な世界観が反映されているのかもしれません。ただ、そういった背景を知らなくても、モダンな絵として鑑賞すること可能なのが、若冲の絵の凄いところで、それ故に人気があるのです。「枡目書き」と呼ばれる技法を使ったこの絵の桝目の大きさはほぼ1センチメートル四方で、枡目の数は両隻併せて86000個あるといわれています。
最新のデジタルの絵にすら通じるところもあるこの不思議な絵が描かれるきっかけは、西陣織の織物の図案に用いられた「正絵」と関係あるのではないかともいわれています。1.2センチの枡目は、西陣の図案の枡目の大きさに合致しますし、若冲の親戚に西陣の人がいたこともわかっています。
いずれにしても若冲の絵は、今、現代の人がぱっと見て、すごいなと思えるものなのです。
日本美術を牽引する江戸時代の美術
ここ十年ほど、江戸時代美術の研究の成果としての展覧会が多く催された時期で、そうした動きをきっかけに日本美術に大きく関心が寄せられた時期でもあります。そして、そのフロントに立っていたのが若冲だと思います。
ここのところの日本美術人気の牽引役はなんといっても若冲なんです。ハイビジョン撮影にも負けないような若冲の絵の凄さと魅力、それが多くの人に伝わって、絵を描く芸術家はもちろん、デザイナーや音楽家なども若冲に注目して、これまで日本美術にあまり目を向けなかった人も巻き込んで、江戸時代にこんなすごい絵があったのかと驚きをもって受け入れられています。
若冲についての情報がこの十何年氾濫しているのに、人気は不動のものとなった理由は、誰もを圧倒する若冲の絵の力によるところが大ですが、そういった力は同時代の京都の画家、応挙や蕭白、芦雪……も持っているものなのです。
鎖国下の日本、しかも京の地で、町人が次第に裕福になり、文化が豊穣に花開いていく、そうした動きのシンボリックな存在として若冲がいるのではないかと思います。
また、いまなお驚きの目で見られているのには、江戸時代の画家として鑑賞されているのではなく、若冲や蕭白、芦雪を「いまの画家」、今の最先端として見ているのではないでしょうか。本巻で、若冲を手始めに、江戸時代絵画の個性に触れ、ますます「日本の美術」の凄さに目覚めていただければと思います。
最後に、伊藤若冲の人気がいっきに華開いたのが2000年京都で開かれた没後200年の展覧会でしたが、1716年生まれの若冲は、まもなく生誕300年を迎えます。画期としての展覧会企画もすでにいくつか進んでいるようです。若冲に限らず、不思議なもので、大きな展覧会が企画されると、大作が出て来ることがままあります。「わかおき」は今や笑い話ですが、未だ見ぬ「若冲」がどこかで発見されることを待っているかも知れません。
(編集担当・清水芳郎)