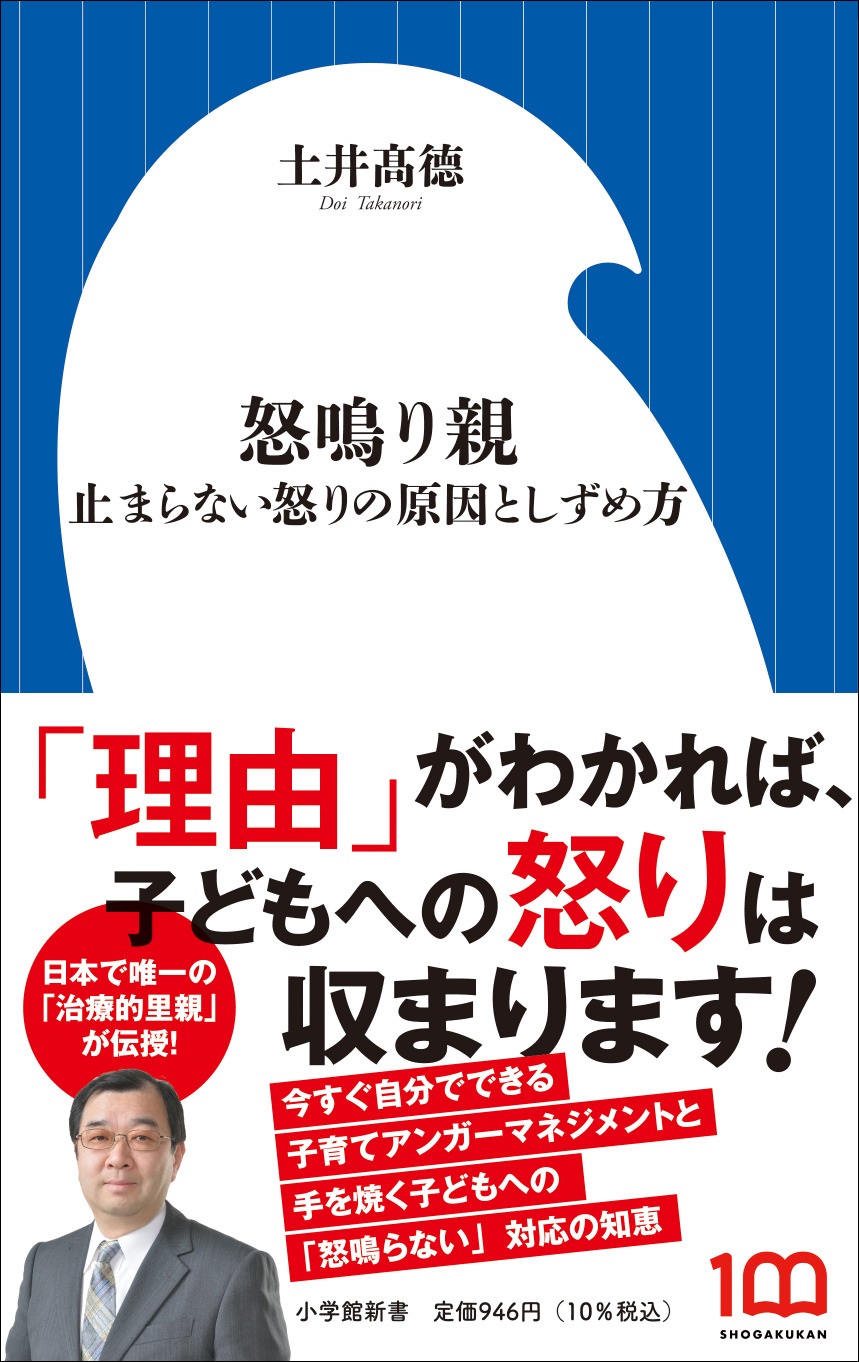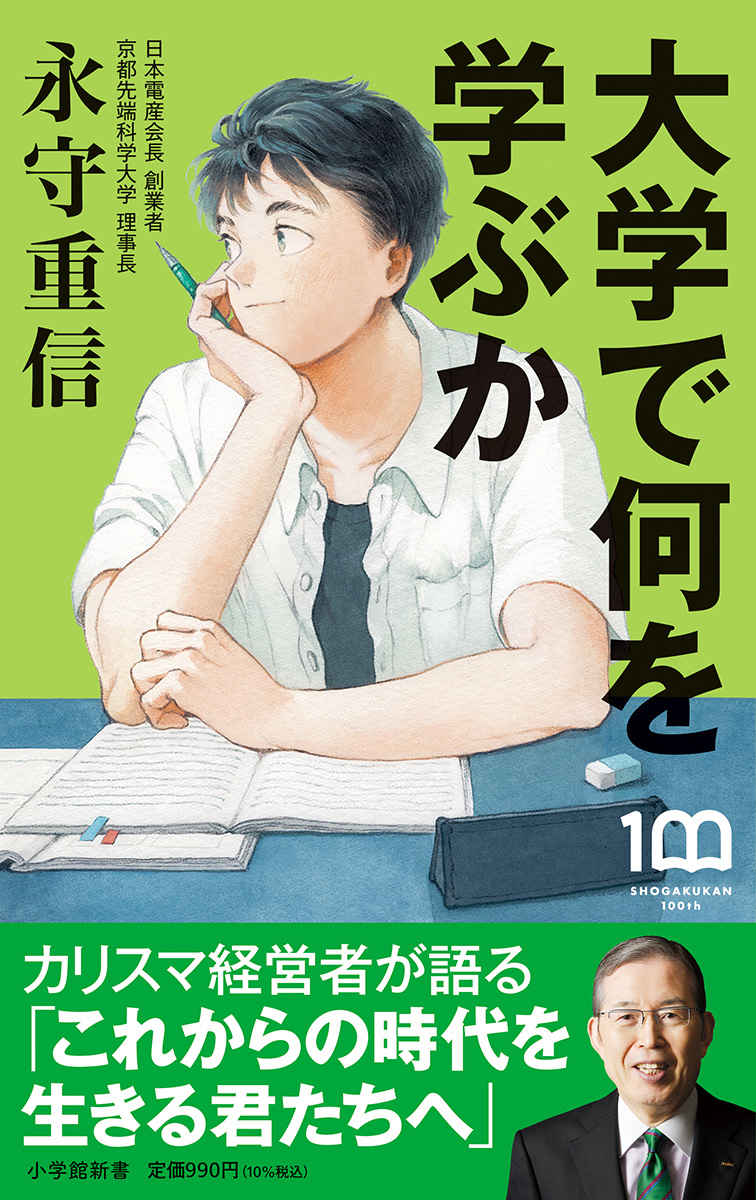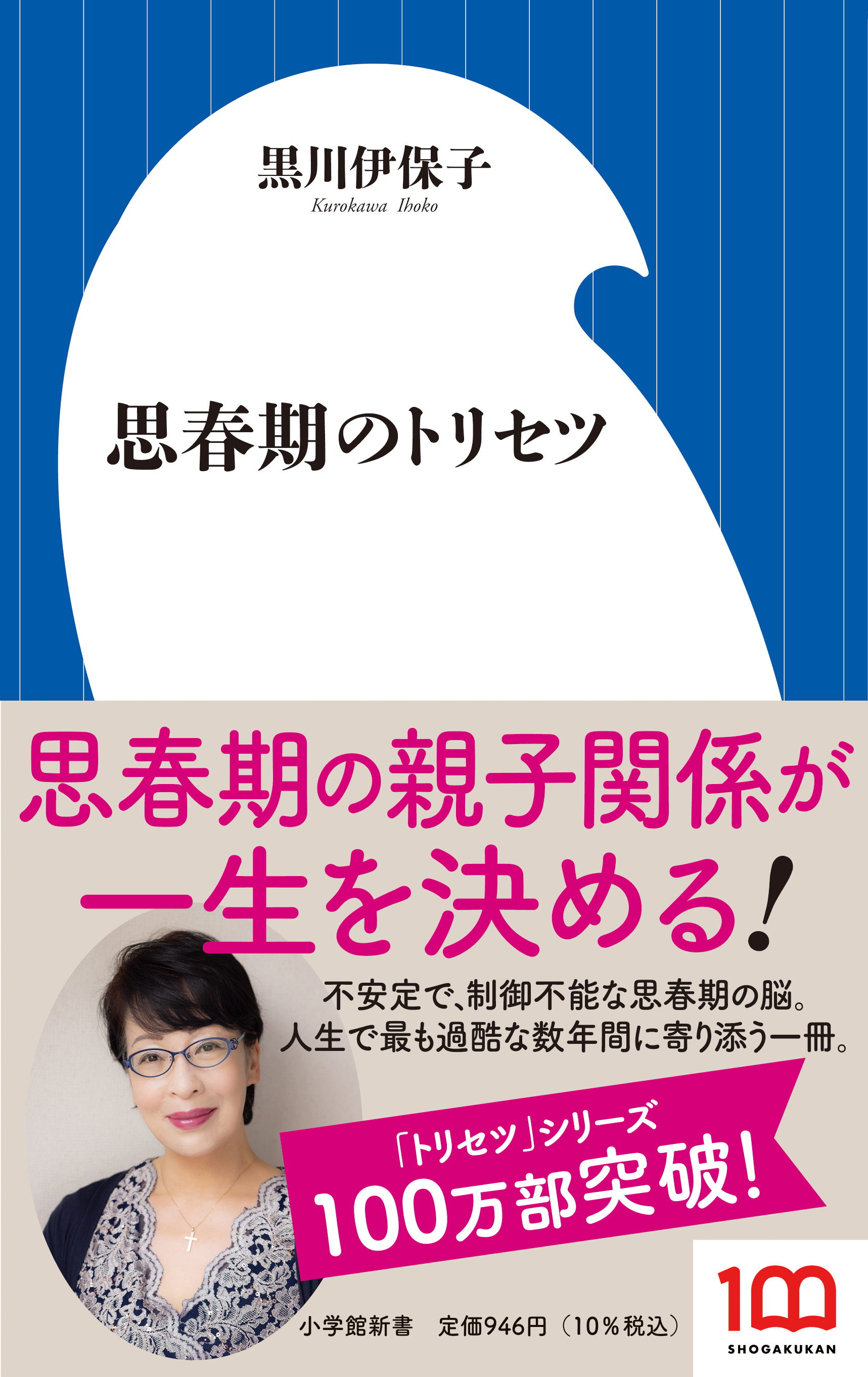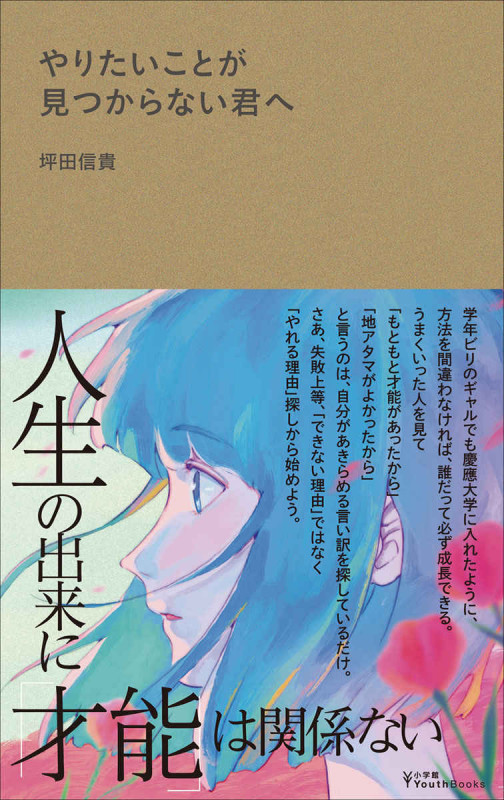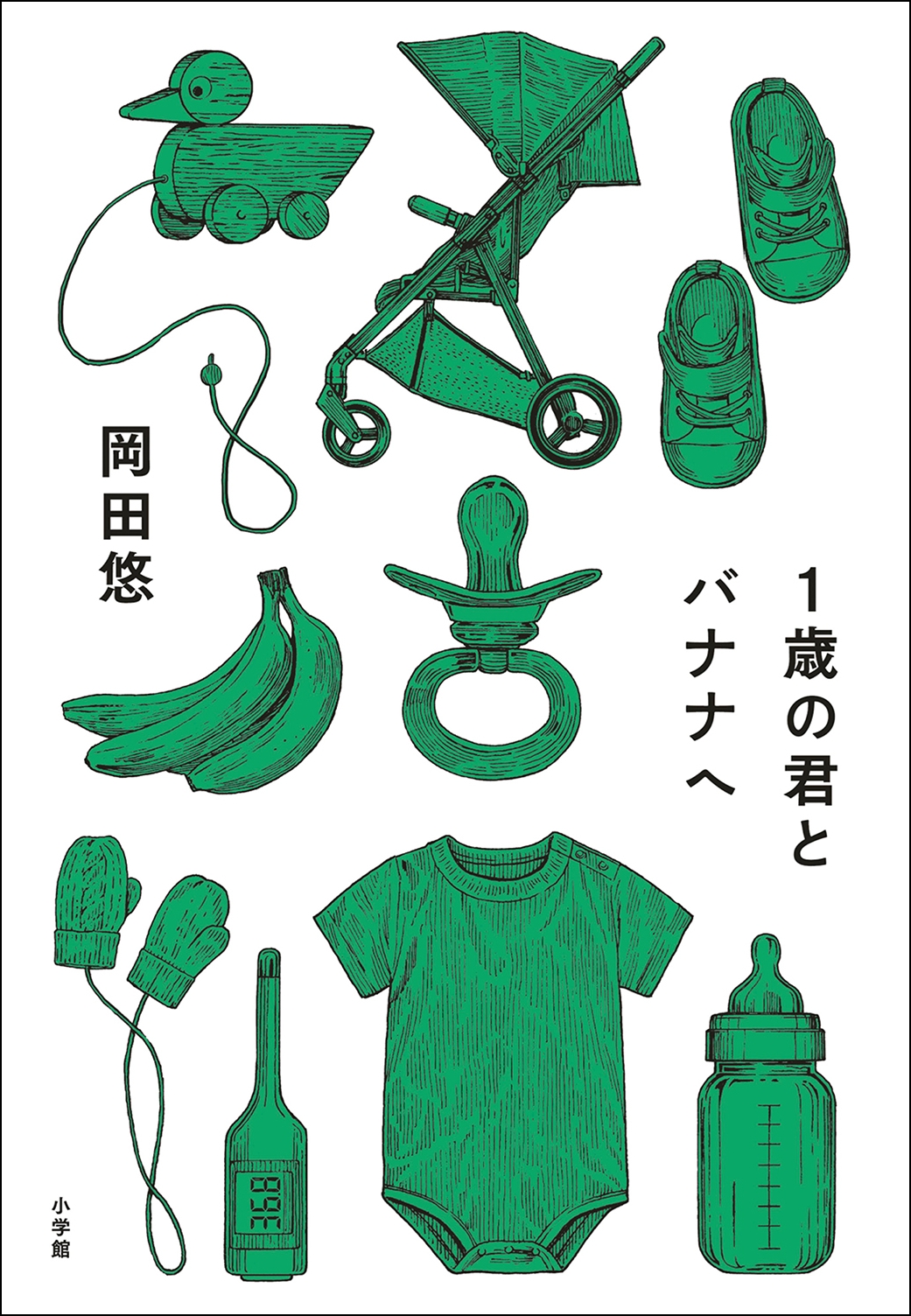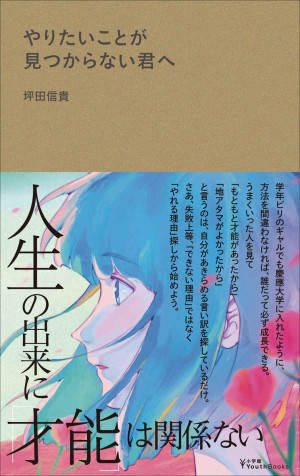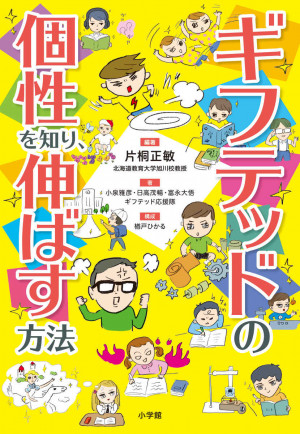お知らせ
2022.10.25
『怒鳴り親』になってしまう「負のスパイラル」を断ち切る方法!
この記事は掲載から10か月が経過しています。記事中の発売日、イベント日程等には十分ご注意ください。
キーワード: 親子 育児 子育て アンガーマネジメント 人間関係 治療的里親 土井ホーム 土井髙德
養育困難と判断された子どもたちが100人以上社会復帰!
日本で唯一の「治療的里親」が綴る「子育てアンガーマネジメント」
「子どもの不機嫌な反応にカチンときて、つい怒鳴ってしまった」「頭ではいけないと理解していても、言うことを聞かない子どもを前にすると怒りを抑えられない」「あんな態度を取るんじゃなかったと、深く後悔してしまう」……。
『怒鳴り親』は、そんな自身の怒りや子どもとの関わり方に悩む親や教師、子どもを支援する関係者らに向けて綴られた、子育てのよろこびを取り戻すための手引書です。
著者の土井高德氏は、心に傷を抱えた子どもを養育する里親ホーム「土井ホーム」(福岡県北九州市)を運営すること半世紀。
里親界の先導者として知られ、家庭や施設で「養育困難」と判断された子どもたちとともに暮らし、100人以上を社会復帰させてきました。
«親子の問題を考えるとき、社会の支援者が子どもの潜在能力を引き出し、子どもに代わって彼らの権利を主張し、守るという観点は欠かせません。が、それと同時に、子どもと深い絆を持つ親や家族にも十分な心くばりが必要だと痛感します。〈中略〉
時代を超えて、親を悩ませる子どもの行動を大きく分けると、2つの方向に分類されます。1つは非行や少年犯罪といった「反社会」的な行動であり、もう1つは不登校に代表される「非社会」的な行動です。〈中略〉
親にとっては目の前の子どもがすべてです。自分の言うことを聞かない。いくら注意しても言動が良くならない……。そんなわが子を前にすると、どうしても平常心を保てず、怒りが収まらない。本書は、そんな「怒鳴り親」のお父さん、お母さん、学校の教師や児童福祉施設の指導員といった大人たちの役に立つことを願い執筆しました。»
(本書「はじめに」より)
【怒鳴り親チェックシート
~こんなことに思い当たる節はありませんか?】
■ 子どもの不機嫌な顔や声だけで気分が悪くなる
■ 子どもの言動にカチンとくる
■ 子どもの反発につい大人げない反論をしてしまう
■ 親を傷つける子どもが許せない
■ 親が傷ついた分だけ子どもも傷つくべきだ
■ 言うことをきかない子どもに、高ぶった感情を抑えられない
➡これらの「理由」がわかれば、子どもへの怒りは収まります!
本書では、「育児は育自」と語る著者が、親自身が今すぐできる「子育てアンガーコントロール」と、手を焼く子どもへの怒鳴らない対応の知恵を伝授!
まずあなたが「怒鳴り親」になってないかの確認から始まり、その怒りの原因をひもとくことで、感情の統制ができるようになるとともに、子どもへの接し方や声のかけ方への理解が深まります。
また、大人に心を閉ざす子どもたちと向き合ってきた自身のエピソードを交えつつ、失敗を踏まえながら構築した「土井ホーム」の子育てメソッドを公開。
子育てに悩む人のみならず、自分自身の感情をコントロールするのが苦手な人にも手にとっていただきたい一冊です。
〈目次〉
はじめに
子どもは切ないほど親を慕っています/親の悩みの種は2つ/人と人との間で「人間」を育む社会へ
第1章 なぜ怒鳴ってしまうのか
あなただけではありません/怒鳴ってしまった実例から/怒りが止まらない原因/子どもに原因がある場合/子どもの「発達」と変化が起きる時期/親に原因がある場合/傷つく前に自分を守っている/子どもの問題は、親の問題
第2章 あなた自身にできる怒りのしずめ方
まず親自身の問題を振り返る/現在は過去の投影/怒りの本質/子育てアンガーマネジメント/良いところをさがす習慣をつける/幼い頃のわが子の写真を眺める/呼吸を整える/ほど良い「間」の取り方を心がける/言葉で心を落ち着かせる/書くことで怒りをしずめる/発達の凸凹の悩みを1人で抱え込まない/気づきがあれば、怒りは収まる/子どもは大事な「預かりもの」
第3章 子育ては、怒鳴らないほうがうまくいく――土井ホームの実践子育てテクニック
怒鳴る子育てにメリットなし/土井ホームの対処方法とねらい/伝えたい内容を視覚化する/子どもの課題は大人の課題/親が準備しておきたい3つの心得/土井ホームの子育てテクニック 基本編/「からだ」から「こころ」に語りかけるアプローチ/親と子が「心のオムツ」をはずす時期/立ち枯れの子、根腐れの子/親にもいろいろある/一貫性と継続性のある「ものさし」を持つ/自立とは、孤立ではない/人に頼っている姿を見せる/2つの固い思い込み/重い荷物を1人で背負わない
第4章 それでも怒鳴りそうになったら――より困難な子に対応するための知恵
親という役割のプロが「里親」/子どもと向き合うときの3カ条/子どもと話す知恵、叱る知恵/ほめるときの知恵/子どもとの距離を縮めたいときの知恵/危険行為と向き合うときの知恵/問題を抱える子どもを見守る知恵/保護者と寄り添うときの知恵/トラブルを解決するときの知恵/マイナスが多いほど、プラスの喜びは大きい/親とは、子どもが安心して迷惑をかけられる存在
第5章 土井ホームの挑戦
家族再生、実現に向かって/土井ホームの3段階の取り組み/興味・関心のあることに光を当てる支援/暮らし自体がトレーニング
あとがき
著/土井高徳
【著者プロフィール】
土井髙德(どい・たかのり)
1954年、福岡県北九州市生まれ。一般社団法人おかえり基金理事長。学術博士。福岡県青少年課講師、産業医科大学治験審査委員。心に傷を抱えた子どもを養育する「土井ホーム」を運営。実家庭や児童福祉施設で「養育困難」と判断された子どもたちとともに暮らし、国内では唯一の「治療的里親」として処遇困難な子どものケアに取り組んでいる。その活動はNHK「九州沖縄インサイド」、「福祉ネットワーク」、「クローズアップ現代」で特集されたほか、テレビ東京、読売新聞、西日本新聞などで紹介されるなど全国的に注目を集めている。ソロプチミスト日本財団から社会ボランティア賞、福岡キワニスクラブから第24回キワニス社会公益賞、北九州市表彰(社会福祉功労)を受賞。著書に『思春期の子に、本当に手を焼いたときの処方箋33』(小学館新書)など。
★ こちらもオススメ!
「偏差値や知名度で選ばない」まったく新しい大学論!『大学で何を学ぶか』
思春期の脳は制御不能、マニュアルなしでは【取り扱い要注意】『思春期のトリセツ』
やりたい「夢」がない人のほうが成功しやすい!?『やりたいことが見つからない君へ』
大人気旅作家が育児という「すげえ」体験を綴る、ニューノーマル育児エッセイ!『1歳の君とバナナへ』
多感で個性的な子どもの潜在的可能性を開花させるコツとは?『ギフテッドの個性を知り、伸ばす方法』
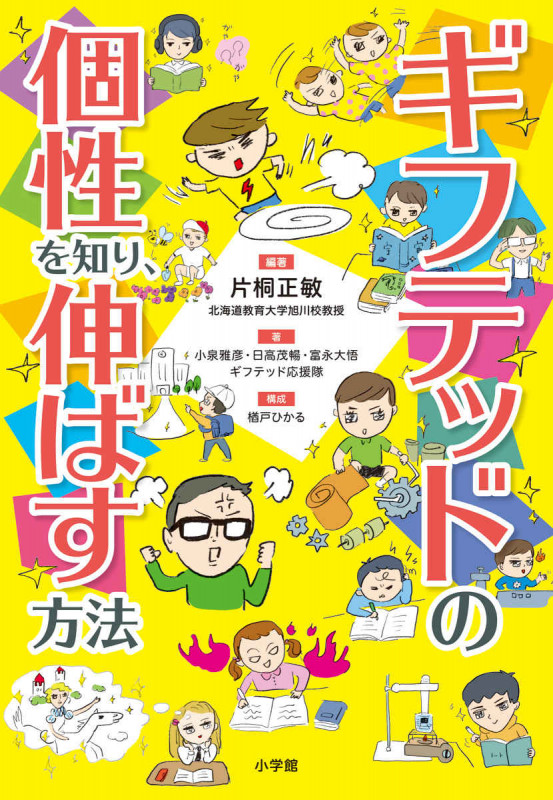
関連リンク