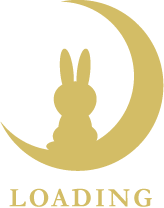
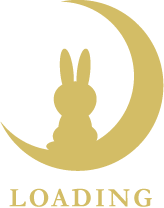


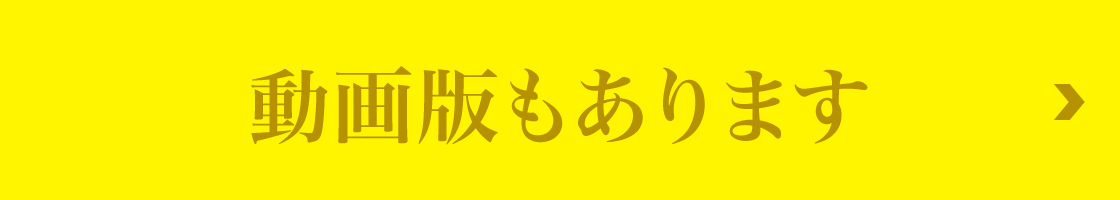


私が小さな頃、テレビで放映した『ドラえもん』の映画を父が録画していてくれたんです。ビデオテープの余った部分には、テレビアニメの『ドラえもん』を入れてくれたりもして。とくに私は「のび太の宇宙開拓史」がお気に入りで、何度も何度もテープがすり切れるくらい毎日のように見ていました。
うちに来れば『ドラえもん』のビデオがあるからと、近所の子どもたちがみんなやって来て一緒に見るような、そんな家でした。『ドラえもん』の映画を見ることに関しては、すごく恵まれた家でしたね。
初めての劇場映画は、小学校に上がる年の春に父と二人で見た「のび太と鉄人兵団」。大きなスクリーンで映画を見たことがなかったのでとても驚いたこと、そして映画にものすごく感動したことを漠然と覚えています。後で父から「おまえ、泣いていたんだぞ」って言われたんですね。それがどうやら、怖くて泣いている泣き方じゃなかったと。自分自身が映画を見て泣いたことよりも、父がそのことをうれしそうに話していたことを、いまでもよく覚えています。
『ドラえもん』という作品には、自分が小っちゃいときにどんな見方をしていたのかという思い出が、家族の数だけあるんでしょうね。そんなところも魅力の一つだと思います。

映画の脚本を書き進めているとき、藤子プロさんから「小説も書いていただけませんか?」と依頼されていたんです。ただ、そのときはすぐに「書きます」とは言えませんでした。マンガやアニメであれだけ面白い『ドラえもん』をあえて小説で書く意味ってなんだろうと…、その答えがなかなか見えてこなかったんですね。
そんなとき藤子プロさんから「小説家である辻村さんにしか表現できない世界があると思うんです」と言われ、そこで初めて自分でも『ドラえもん』を小説で書くということに向き合ってみたんです。脚本ができあがると、監督をはじめスタッフのみなさんはそれから1年半をかけ、公開に向けて映画を作り続けます。私も小説を書くことで、もう一度この物語に向き合う機会をもらえたのだと思います。
最初の1行、「月は、人が生きるには過酷な世界だ」という一文が自然と出て来た時、「あっ、これは脚本とは全然違うものだ」と気づいたんです。ただ脚本のストーリーやセリフをなぞるのではなくて、映画とは違うアプローチで演出まで自分で書くことなんだと。自分の本来の場所に帰ってきた感じがしました。脚本をベースに監督が映画を撮るように、私は私で、もう一つの映画を撮るような気持ちで小説の中に飛び込んでいったんです。映画と小説の両方をそれぞれの角度で楽しんでもらえたら、とてもうれしいですね。
それにしても、藤子・F・不二雄先生って本当にすごい! もともと偉大な、すごい方だと知っていたはずなんです。そう思っていたからこそ脚本を引き受けるかどうかもあんなに迷っていたのですが、実際に自分で『ドラえもん』のお話を書いてみたら、先生に近づくどころか、より遠ざかったというか…。長年にわたって本当にすごいお仕事を、締め切りがあるなかで日常的に続けてこられた漫画家さんだったんだなと。映画の仕事を通じて、より尊敬の気持ちが高まりました。


小説と脚本の流儀は、まったく違うものでした。たとえば登場人物の長いセリフ。小説では読者に状況や気持ちを伝えるために言葉を尽くしがちですが、映画は違う。「声優さんの演技と絵があれば充分に伝わりますから、このひと言で大丈夫です」と監督に指摘されたところが何カ所かありました。その言葉を聞いたとき、小説でできること、そしてアニメでできること、それぞれ得意な部分があるんだなと気が付いたんです。同じアイデアや設定から発信しても、アプローチの仕方がこんなに違うんだと。勉強になることがとてもたくさんありました。
脚本を書いていて、まるでドラえもんのひみつ道具みたいだと思ったんですよ。「ミステリアスな月」って書いたら、書いた本人はそれが何色なのか知らなくても、「ミステリアスな月」がアニメでは仕上がってくるんです(笑)。なんて素敵な道具なんだろう、これはひみつ道具を手に入れたようなものだと。他にも、「荒涼とした大地」と書いておけば、「荒涼とした大地」が絵になってできあがってくる。すごく楽しい!とはしゃいでいたんですけど、いざ小説にするとき、その作業がすべて自分にはね返ってきたんです。ああ、私が一人で描写しなきゃいけないんだって(笑)。
この小説は、自分が脚本で書いたものって何だったんだろうと、その意味をひとつひとつ再確認するような気持ちで書きました。できあがっていくアニメの絵を参考にして書いた部分もありますが、もちろんそうではないところも。たとえば、このとき登場人物がどんな思いでいたのか、といったような部分ですね。そうした部分を書くことが本当に楽しくて。すでに絵のある場面のほうが早く書けると思っていたら、そうではなかった。何もない、一から文章で描写して書かなければいけない場面や映画にはないシーンのほうが、楽しみながらスピード感を持って書くことができたんです。私はやっぱり小説家だ。ここで生きているんだなって。

最初は子どもに読みやすいようにと思って小説を書いていましたが、途中からあんまり考えなくなりました。文章が難しいと思う子どもがいるかもしれないし、逆に簡単すぎると思う大人がいるかもしれない。けれど私は子どもの頃に、『ドラえもん』を子どもだけのものだと思って読んでいたわけではありません。大人になったいまも同様です。子どもも大人もみんな、『ドラえもん』が好きなんですよね。だから普段の小説を書くときと同じよう、年齢に関係なく読んでくれる人が読んでくれたらいいなと思って書きました。
もしも子どもが読んだとき、わからない言葉が出てきたら、その言葉の意味を前後の文章から想像してもらいたいですね。そうやって言葉を覚えてくれたらうれしいです。私自身、子どものときにそういう読み方をしてきたように思いますし、漢字もそうやってだいぶ覚えた。今回、ジュニア文庫版が出るので、そこでは漢字のフリガナもすべてつくし、あえてひらがなを多用するというのもやめました。
もうひとつ、『ドラえもん』を小説で書くにあたって、私の背中を押してくれたのが、瀬名秀明先生の『小説版ドラえもん のび太と鉄人兵団』の存在でした。瀬名さんが『鉄人兵団』を書かれたとき、編集者から「のび太たちの年代が読めるように」と最初は依頼されたそうなんです。そしたら瀬名さんが「のび太たちじゃなくて、(『エスパー魔美』の)魔美が読めるくらいでもいいですか?」とおっしゃった。そのやりとりを伺って、なんてオシャレで、すてきな返し方をされるんだろうと思ったんですね。ノベライズの依頼を受けて、真っ先に思い出したのがその言葉でした。その言葉が私の中でも基準になって、最後まで書き上げることができた。もともと私は学生時代、瀬名さんが「『ドラえもん』が好き」とインタビューなどでおっしゃっている姿を見て、いつか、自分も作家になったら「『ドラえもん』が好き」と言える作家になりたい、と思っていたんです。なので、私を今回の映画につないでくれたおひとりは瀬名さんだったと思っていますし、瀬名さんの『鉄人兵団』がなかったら、書き出すときにもっとずっと迷ったと思う。瀬名さんにも、心から感謝しています。


大長編や映画の中で、ドラえもんたちが冒険していないところはほぼないんですね。藤子先生が「『ドラえもん』の通った後は、もうペンペン草も生えない、というくらいに、あのジャンルを徹底的に描き尽くしてみたい」とおっしゃっていましたが、本当にその通りでした。
そうした中でなんとか見つけた冒険の舞台が月だったんです。実は、これまで何度か映画のスタッフの方たちも月を舞台に作品を作ろうとしたそうです。けれど、どうしてもかなわなかった。もしも長い『ドラえもん』の映画の歴史の中で、一度だけ月面着陸がかなうなら私にやらせていただけないだろうかと。そう思って月を舞台にしたいと提案しました。
まだどんな物語にするのかも固まっていなかったんですが、スタッフの一人から「辻村さんの名前にも月が入っていますしね」と言われたんです。それを言われたら、もう後には引けないなと。実はまだ引き返せると思っていた部分もあったんですが、そこを指摘されたため「ああ、もう腹をくくるしかない」と覚悟が決まりました(笑)。

「のび太!」
野比家の朝、いつも聞かれるママの声が、この日も、家全体に響き渡った。
その声に「はいはいはーい!」と応えるのは、この家の長男・野比のび太。
遅刻が多く、ドジで、運動も苦手、学校の成績も0点続きの──だけど、とても優しい、メガネをかけた小学生の男の子だ。
(『小説 映画ドラえもん のび太の月面探査記』
第一章より)
のび太がどういう子なのかっていうのは、この小説を読んでくれる人なら誰もが知っているでしょう。けれど、私はきちんと文章で紹介したかった。小説を引き受けたときから、絶対にそれだけはやろうと決めていました。なぜなら、私が子どものときに読んでいた児童文学の多くが、そのお約束事を守っていたから。そんな本が、自分にも書けたらいいなと思ったんです。
私は那須正幹先生の「ズッコケ三人組」シリーズが大好きでした。全50冊のシリーズがある中で、どの巻でもかならず「この口の悪い少年がハチベエ」といったふうにキャラクターが紹介されているんですね。子どもの頃は「毎回、同じことが書いてあるなあ」くらいに思っていたんですが、最終巻ですらそれが書いてあるのを大人になってから知って、「ああ、子どもたちがどの巻から読み始めても、それがズッコケ三人組との最初の出会いになるように、先生がそうやってらっしゃったんだ」と気がついたんです。
私も同じようにしよう。のび太やドラえもんのことはみんなが知っていると思うけど、もう一度読んでねという気持ちで、あえて彼らをきちんと紹介しようと。もしかしたらこの本で、初めてドラえもんに出会う子どもがいるかもしれない。そう想像することが、子どもをなめないことだと「ズッコケ三人組」と那須先生に教わったんです。


私が、のび太のセリフを書いちゃっていいのかな。ドラえもんに自分の考えたセリフをしゃべらせていいのかな。最初はそういう気持ちがとても強かったです。けれど、あるとき、藤子先生のチーフアシスタントをされていたむぎわらしんたろう先生から、こんなメールをいただきました。「映画ドラえもん、楽しんでください。ドラえもんたちもきっと、新しい世界へ冒険に行けることを楽しみにしているはずですよ」と。
むぎわら先生自身も、藤子先生がいなくなったあとの映画を引き継いできた1人でもあるので、本当に大変だったと思うんです。けれどそのメールを読んで、確かに大変だったかもしれないけれど、むぎわら先生も、ドラえもんたちと冒険したことはきっと振り返ってみたらとても楽しかったんだろうなと思えたんです。じゃあ、私も楽しむことを考えよう、と。地底、海底、宇宙、これまでドラえもんたちにいろいろな場所へ冒険に連れていってもらったけれど、今回は自分がドラえもんたちの手をとって冒険に連れて行く係なんだ。その役割を楽しもうと。気持ちが切り替わってからは、胸をはってドラえもんたちのセリフを書くことができた気がします。
小説を書いているとき、私の頭の中で動いていたドラえもんやのび太には3パターンの姿がありました。一つは原作まんがのドラえもんたち。この割合がいちばん多かったかもしれない。ドラえもんの頭もつるっとした青色ではなく、ペンで描いた縦線模様でした。二つめは私が小っちゃいときに見ていた、大山のぶ代さんが声をあてて芝山努監督の演出で動くドラえもん。そして三つめが、水田わさびさんの声で動くいまのドラえもん。とくに金曜日にうちの子どもたちとアニメを見たあとはそうなるんです(笑)。戦闘シーンなどでは、いまのドラえもんたちの声や動きを想像しながら書くことが多かったです。執筆中はまだ声優さんたちにはお会いしていなかったんですが、テレビ画面の向こうから声優さんたちに助けてもらっているような気がしていました。
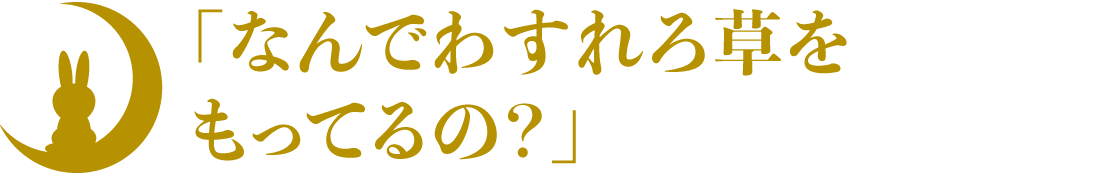

原作まんがに登場するひみつ道具をたくさん出したいな、という気持ちがありました。映画や小説を楽しんだ人たちが、「原作まんがではどんなふうに使われているんだろう」とコミックスに戻ってきてくれたら、と。
とくに「わすれろ草」は、コミックスの表紙にも描かれている道具なので絶対に使いたかった。映画の予告を見たうちの息子が、「なんでしずかちゃんがわすれろ草をもってるの?」と、一瞬しか映らないカットにもかかわらず、すぐに気づいてくれて。ああ、このフォルムだけで「わすれろ草」だとすぐにわかるんだと感動しました。同じように多くの大人たちにも、「うちにあったコミックスの表紙に描かれていた花だ!」と気づいてもらえたらすごくうれしいです。
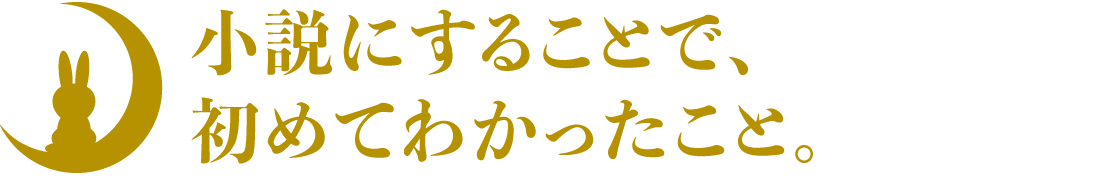
小説を書いていて、「あ、ここが自分の本領発揮だ」と思えた場面がいくつかあるんです。とくに各章をつなぐインタールード(芝居の幕間、音楽の間奏曲の意味)は、本当に自分がノって書いているなって。インタールードのある一場面では、ルカがどういう子なのか、より深く知ってもらえる内容になっています。それは文章で綴る小説だから書けた場面だと思っています。
小説にすることで、初めて言葉にできたキャラクターの気持ちや事情がいくつもあるんです。普段の小説でも、書きながら登場人物の気持ちがわかることがよくあるんですが、今回のように完成させた脚本があっても同じことが起きるというのは、自分にとって発見でした。
おそらくそれは、ルカたちが私だけで作ったキャラクターではなく、スタッフのみなさんと一緒に作ったキャラクターだったからかもしれません。もともとの設定に厚みや奥行きがあったからこそ、自分の筆で書いてみたとき、よりふくらませていくことができたんでしょうね。

『ドラえもん』がこれだけ長く愛されているのは、きっとみんなのものだから。そして、ずっといまのものだからではないでしょうか。先日、息子が「大魔境のDVDを見たい」っていうので「昔のやつ? いまのやつ?」と聞いたんです。1982年の「のび太の大魔境」と、2014年のリメイク版のどっち? という意味で。そしたら息子が「昔のってどういうこと?」って。私が説明しようとしたら、「両方いまのだよ」と言うんです。昔のとか、いまのとか、リニューアル前とか、リニューアル後とかって、私たち大人はつい口にしてしまいますけど、子どもたちにとってはどの作品も並列して、みんな「いまのドラえもん」なんです。
みんな等しくシリーズの1本ですから、どの作品が『ドラえもん』との出会いであってもいいんですよね。今年の映画が最初の出会いになる人がいるかもしれないし、過去の作品がそうなるかもしれない。決して特別なものではない、シリーズの39分の1作品として、『ドラえもん』の映画に参加することができたことをすごく幸せに感じています。
感動には、大人も子どももありません。中高生や大学生はもちろん、私と同年代くらいの大人世代や、私くらいの娘がいるそれより上の世代の人たちだって、みんな心に残る『ドラえもん』の思い出があるはずです。今回の映画や小説をきっかけにそれぞれの思い出と再会し、「あのときに見た映画をもう一度見てみようかな」「コミックスを読み返そうかな」と思ってくれる人がいたら、こんなにうれしいことはありません。
