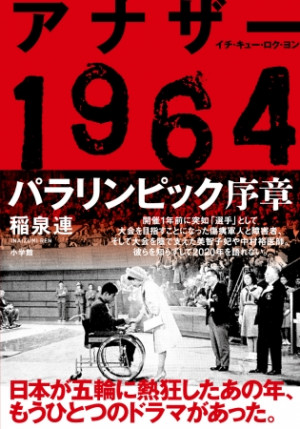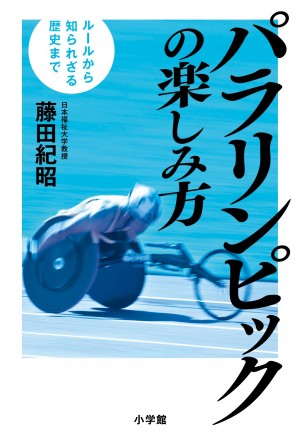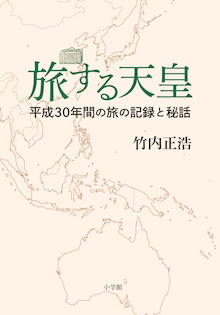お知らせ
2020.3.20
「患者」から「選手」へ。日本人の概念を変えた知られざる物語。『アナザー1964 パラリンピック序章』
この記事は掲載から10か月が経過しています。記事中の発売日、イベント日程等には十分ご注意ください。
あの日、彼らは初めて「主役」として舞台にあがった!
1964年のパラリンピックが教えてくれたもう一つの視点。
日本列島が五輪に熱狂した1964年。
知られざるもう一つの物語が進行していました。
東京でのパラリンピック開催です。
決まったのは1964年の僅か1年前のこと。
これは、ある東京パラリンピック出場者の回想です。
「当時の日本は、やって来た外国人から『日本に障害者はいないのか』と聞かれていたような時代。息子も娘も出るのを嫌がって、家族も出すのを嫌がって、みんな家の中に引っ込んでいたんだから」
高度経済成長に沸く日本にあって、日本の障害者は社会から追いやられた存在でした。
当然、障害者スポーツという概念すらなく・・・。
当時は「患者」とされていた脊髄損傷の人たちが、一部の医師の勧めによって競技場に集められました。
彼らは競技のルールもほとんど知らないまま大会に出場し、大きな衝撃を味わうことになります。
例えばそれは、海外選手たちが実に楽しそうに競技に打ち込み、オフには東京の街を車椅子で散策していた姿です。

戸惑う日本選手たちの背中を押したのが、後に障害者の自立施設「太陽の家」を設立する医師・中村裕氏や、大会招致にも深く関わった美智子妃殿下(当時)らでした。
本書では、大宅賞作家が5年の月日をかけて、1964年大会を支えた関係者たちを取材。
パラリンピックの舞台裏に迫ります。
‹‹パラリンピックの物語に深く分け入れば分け入るほど、私はこれまで語られてこなかった戦後史の一端に触れているように感じた。››
(本書「あとがき」より)

1964年のパラリンピックが日本にもたらしたものとは?
急ごしらえで大会準備が進められる中、急遽「選手」となった障害者たちの思いは?
大会運営を陰で支えた美智子妃殿下の知られざる奮闘・・・。
そもそもパラリンピックはどこから来て、世の中に認知されたのか?
開催をめぐるさまざまなエピソードは驚きの連続です。
2020年大会を前に、ぜひ皆様に知ってもらいたい入魂のノンフィクション!
貴重な写真も多数収録しています。

著/稲泉 連
【著者プロフィール】
稲泉 連(いないずみ・れん)
1979年生まれ。『ぼくもいくさに征くのだけれど: 竹内浩三の詩と死』で大宅賞受賞。主な著書に『復興の書店』、『豊田章男が愛したテストドライバー』、『「本をつくる」という仕事』、『宇宙から帰ってきた日本人』など。
☆こちらもオススメ!
・〝どん底〟のトヨタ自動車社長を支えたのは、開発中の事故でこの世を去ったテストドライバーだった。 『豊田章男が愛したテストドライバー』
・パラリンピックを観戦しよう! 『パラリンピックの楽しみ方』
・1964年の東京オリンピックを支えた人々の感動秘話!小学館文庫『TOKYOオリンピック物語』
・天皇陛下は日本一の旅人である。『旅する天皇 平成30年間の旅の記録と秘話』
関連リンク