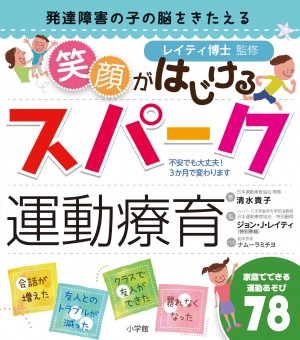お知らせ
2016.5.20
脳を活性化させるには運動がイチバン! どの子も3か月で変わる!! 『発達障害の子の脳をきたえる 笑顔がはじけるスパーク運動療育』
この記事は掲載から10か月が経過しています。記事中の発売日、イベント日程等には十分ご注意ください。
運動をすると、ほかのどんな活動より
脳細胞が活発に働きます!
「運動は、体だけに効果があると皆が思っています。たしかにその通り、筋力アップには運動が不可欠です。が、絶大な影響を受けるのは実のところ脳なのです。脳には1,000億を超える細胞があり、何をするにも、その一部を使うわけです。そして、どの活動よりも運動が最も広範囲に脳細胞を使います」(ハーバード大学医学大学院准教授・医学博士・スパーク運動療育特別顧問/ジョン・J・レイティ)。
発達障害をもつ子の「脳の発達」「新しい脳神経をつなぐこと」を目的とした運動療育=「スパーク運動療育」は、日本運動療育協会理事であり、本著の著者である清水貴子さんと、レイティ教授との出会いから生まれました。
「自閉症スペクトラム障害、注意欠陥・多動性障害、学習障害など、脳の特性が違うもつ子どもの親御さんは『うちの子は脳の配線が違うんだ』と考えてください。まずそれを受け入れ、恥ずかしいと思わないこと。大切なことは、子どもが体を動かすようにすることです。注意力や学習に困難があっても、そして自閉症スペクトラム障害の症状があっても、体を動かすことで脳も行動も改善します」(レイティ博士)
元々、精神疾患の予防のために運動指導をしていた清水さんは、レイティ博士の話から「この分野でも役に立てる!」と思い、「スパーク運動療育」の開発をはじめました。具体化したのは2012年夏。東京都から指定を受けて児童発達支援事業所「スパーク代々木センター」をオープン。子どもの興味を生かしながら子どもの意思で楽しくからだを動かし遊ぶという療育で、発達障害の見られる何百人もの子ども達の改善効果が報告されています。
「入学して分かった、対人感覚が個性的で友達の輪に入れない状況。発達精神科通院の後、紹介され、この運動療育を4年生から開始。初日から瞳が輝き笑顔に! 最近はクラスの子と行動出来るようになった」(小6男児)
「1年も経たずに表情が改善。人の気持ちを考えられない子だったのに笑顔が増え「ありがとう」が言えるように。学校も楽しく友達もできた(小5女児)
「苦手な運動はしない、自己主張の強い子だった。スパーク運動療育1回目で、一段ずつ足を揃えてしか降りられなかったのに、早くも駅の階段をふつうに降りられるように! 自己肯定感が高まり挑戦できるように成長」(小2男児)
この「スパーク運動療育」を家庭でもできるように、と初めて書籍化しました。本書ではおもに発達障害のある子どもをもつ家庭向けに、スパーク運動療育の考え方と、スパークで実施し、効果が現われている運動遊びを紹介しています。この考え方と遊びは、どんなお子さんにも、大きな効果があるものです。ぜひ、子どもと一緒にチャレンジしてみてください!
「<運動機能>からだを動かす、<感覚>五感を使う・刺激する、<感情>感情に働きかける、子どもの成長の、この3つの"根っこ"に働きかけるスパーク運動療育。人間の「脳力」は、これでたくましくなる、と体験した子ども達の様子を見て痛感しました。『学習能力も高まる』というのも、腑に落ちます」(担当編集)
『発達障害の子の脳をきたえる 笑顔がはじけるスパーク運動療育
著/清水貴子 監/ジョン・J・レイティ イラスト/ナムーラミチヨ
関連リンク
-
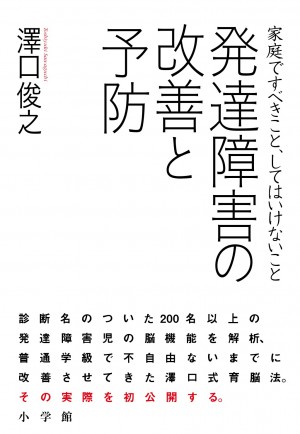
スマホ・喫煙はNG! 高齢出産を避ける!(特に父親) 英語の早期教育は問題! 子どもの「発達障害」を防ぐためにできること。 『発達障害の改善と予防』
-
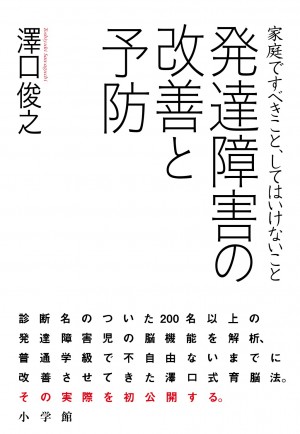
世間の常識は脳科学的には非常識! 200名以上の発達障害児の脳機能を改善した方法とは? 『発達障害の改善と予防』
-
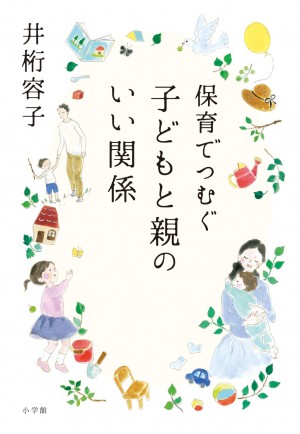
東京家政大学ナースリールーム主任保育者が提案!子育てと共に、親もまた育っていく「友育ち」のために必要なこと! 『保育でつむぐ 子どもと親のいい関係』
-
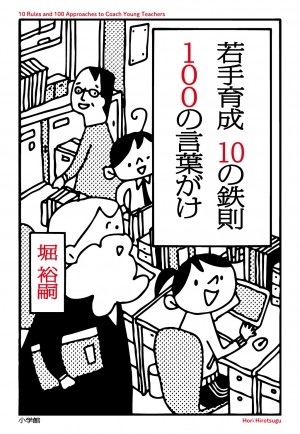
アラフォー以下は、「自律」より「承認」を求めている! 教育のプロが教える『若手育成 10の鉄則 100の言葉がけ』
-

6つのテーマで「串刺し」にすると、”世界のカラクリ”が見えてくる。 『池上 彰の世界の見方 15歳に語る現代世界の最前線』